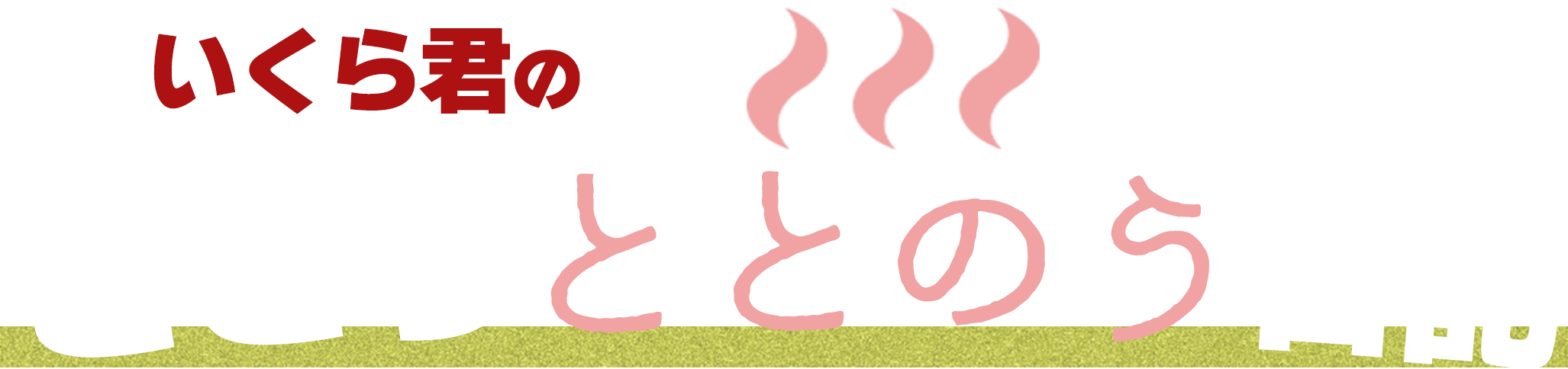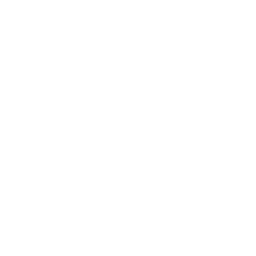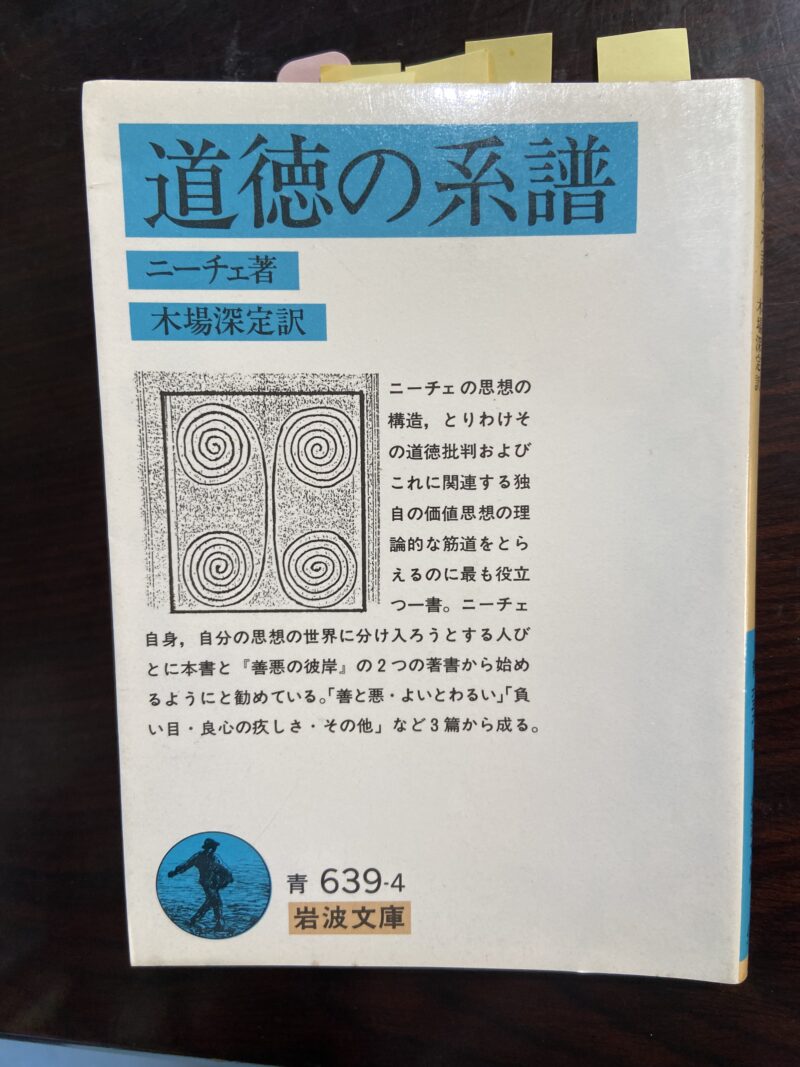ニーチェ『道徳の系譜』読了
前回の『善悪の彼岸』に引き続きニーチェ『道徳の系譜』(1887)である。ニーチェの大著『ツァラツストラかく語りき』はあまりに文学的なため,ニーチェの思想が誤って伝わるという心配から彼は『善悪の彼岸』を書いたが,それも箴言が多く一般に理解されない心配があり,それを補佐するために本書は書かれたという。
いわば,彼の中期の思想をもっもとわかりやすい散文で書いたものである。
第一論文はいわゆる「善悪」という従来の道徳的価値判断の起源を暴き出すことが中心問題であって,この勿体らしい判断方式の正体は,キリスト教的な奴隷人間の恨みっぽく悪賢い「ルサンチマン」の精神から生まれた奇形児で,その本質から言えば,古代的な貴族人間に対する一つの反抗運動であり,貴族的価値判断の支配に対する大規模な暴動に他ならない。(解説より)
第二論文は「良心の心理学」を提示する。良心とは「内なる神の声」などではない。「良心」の創始者は却って,外に向かって放出することがもはやできなくなった後,逆転して内に向かう「残忍性の本能」である。(解説より)
第三論文は「禁欲者の心理学」である。「禁欲主義的理想」(僧職的理想)の巨魁な力はどこに由来するか。「禁欲主義的理想は何にもまして「有害な理想」である。(解説より)
我々の内面に巣食う,自己呵責の由来を明らかにして,2000年間我々人間を苦しめていたものからの解放をたからかに歌い上げる。これがニーチェのやりたかったことなのだろう。
それがある時は壮大な詩的言語によって,あるいは散りばめられた箴言によって,そして本書のように散文によって。彼によればプラトンもカントもけっちよんけっちょんだ。とにかく,現在のベースとなった常識をぶち壊す。
いずれにせよ,頑丈な鎖に縛り付けられた当時の人々(それは2020年台の現代においても同様である)の心をこじ開けることは難しかったであろう。彼の理解者は少なく,貶めようとする勢力にたいそう辛い思いをしたに違いない。
「人間は何らかの仕方で,少なくとも心理的には,さながら檻の中に閉じ込められた動物か何かのように,理由も目的もわからずに,自己自身によって苦しめられている」(第三論文20)
「より善くする」とは「飼い慣らす」とか,「弱くする」とか,「沮喪させる」とか,「柔弱にする」とか,「去勢する」というほどの意味だ。(第三論文21)
全くもって共感する。その通りだ。この世は巨悪に塗れて,我々は内面から苦しんでいる。圧政によって苦しめられているのではない。自らの心に「善」とか「道徳」といった形で,苦しみの根源が埋め込められている。いわばOSに組み込まれているのだ。だからシステムを再構築しなければならない。
でもね。それはたいそう疲れることであろう。大風に向かって歩き続けることなのだから。彼は「強くあれ!」と我々を煽る。畜群と言って罵り,我々のうちならプライドを刺激しょうとする。
でもやはり,耳を塞いで下を向き,畜群として生きていかざるを得ないのだろうな。強くないから。悲しい? 老人だから?