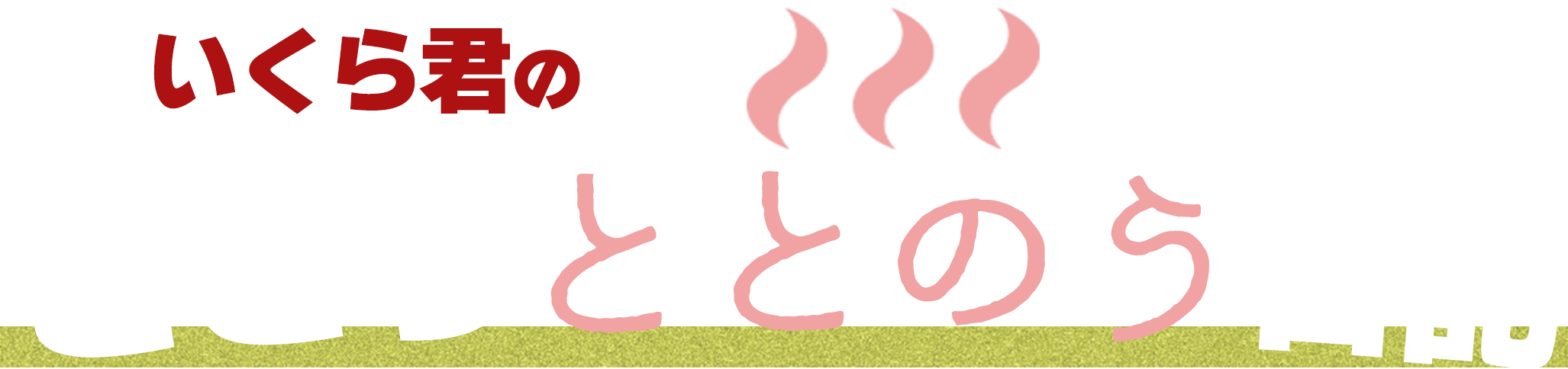メルビィル『白鯨』読了。

メルビル『白鯨』ようやく読了。長かった。岩波文庫版で上中下三巻、ページ数は1000オーバー。1ヶ月間この作品と格闘した。
作者はハーマン・メルビル(1817〜1891享年72歳、米国)である。小説だけでは食えずさまざまな職業を経験した苦労人である。本作の名を知っている人間はとても多い。生前には世間に認められなかった本作も、彼の死後高い評価を得ることとなり、今ではアメリカ文学の代表的作品の一つとして数えられる。ところが、意外に読了した人間は少ないという話がある。長さ、退屈さなどによると推察される。それは翻訳の問題も大いにある。私が読んだ今回のものも、何せ、訳が古かった(私の手元にある岩波文庫は阿部知二訳初版は1956。その後改訂されていない。ちなみに現在の岩波文庫は八木敏夫訳でありこちらの方が読みやすそう)。その上、原文も相当時代性を表していると思われる。それも魅力の一つなのだが。
時は日本史的にいえば江戸時代(19世紀前半)。当時アメリカでは捕鯨が大変盛んであった。周知の通り日本近代化のきっかけはアメリカの捕鯨文化である。鯨から採れる油が灯明用として大変需要が高い上に、また、肉・皮・骨・龍涎香(鯨の腸内から採取される香料)などいずれも珍重されたようだ。彼らは鯨を追い、ニューヨークを出港し、希望峰・印度・マレー半島・台湾を通過し、はるか東(極東)の島国日本沖まで船を走らせるのだ。船上で仕事をし、毎日同じ顔を突き合わせ、無事帰還するまで数年、ストレスも相当なものであったに違いない。大変な時代であった。しかし、未知との遭遇という浪漫がまだまだ大いにあった時代でもある。
物語の大筋は、「モビィ・ディック」と名付けられた白い巨大(体長20mくらい?)なマッコウクジラに以前片足を食いちぎられ、その復讐に燃える「捕鯨船ピークォド号」「船長エイハブ」が陣頭指揮にあたり、命を顧みず白鯨を追い求め、遥か太平洋日本沖まで旅をする海洋小説である。海洋小説であるが、冒険小説ではない。著者の主眼は冒険には置かれていないからだ。
語手は船員「イシュメイル」。当初は一人称で登場するも、じきに物語には登場しなくなり語手に徹する。イシュメイル初め多くの男たちが捕鯨船ピークォド号の乗組員となりニューヨークを出港する。しかし、なかなか船長エイハブは姿を見せない。船長室から出てこない。居るのにいない。このことが船員たちの妄想を膨らませる。みな噂でのみで彼の経歴を知る。以前捕鯨船乗組員(の中でも花形である銛手)であった若かりし日のエイハブはその時の航海で「モビィ・ディック」に片足を齧られ、今は膝下鯨骨の義足をつけている。また、かなり傲慢で偏屈な人間であるらしい、etc。
そして出航後数日して、老船長エイハブは皆の前に姿を現し、本航海の目的を告げる。つまり、この航海は「モビィ・ディック」への復讐の旅である、と。金で雇われた船員たちにエイハブは私怨を晴らすことを強いる。当初困惑した乗務員たちもエイハブ船長の異様なまでの執念に圧倒され次第に共感していく。つまり、一丸となって「モビィ・ディック」を探しあて、銛を突き刺すことを夢見るようになる。それに対峙するのが一等運転士「スターバック」である。米国に家族を残している彼は、エイハブに敬意の念を持ちつつ、冷静に彼の蛮行を批判する。時にはピークォド号が無事ニューヨークに帰還するためには、エイハブ船長を殺害するしかないと思いつめるも、結局それにも及ばない。ちなみにコーヒーチェーン「スターバックス」は彼からきているらしい。創業者が3人いたので複数形にしたということである。
さて、先に、この小説は海洋小説ではあるが、海洋冒険小説ではない、と、書いた。冒険譚ではないということだ。その手のハラハラドキドキで読者の興味を惹きつけ、最後にカタルシスを感じさせるもの、とは種類を異にするのである。大きな柱は復讐の船旅ではあるが、それよりも、船員の出自・性格・肌色を細かい描写、あるいは、鯨の種類・生態に対する説明、捕鯨の方法論、船の構造、鯨の肉体的特徴、鯨の捌き方、またその油の量・質・匂いの凄まじさ、時に出会う他の捕鯨船との交流等々、白鯨を求め航海するという大きな柱に様々な髭根が絡みつく。それもシェイクスピアの芝居のような大仰な台詞、また旧約聖書やギリシア神話からの多くの引用など、ラストに向かい作者の筆は寄り道だらけで全く急いでいない。まるで、長い長い退屈な船旅のようだ。小説の構造自体が船旅のメタファーになっている。それが物語の大きさになっている。
また、乗組員は白人、アフリカから連れてこられた奴隷の末裔、あるいはネイティブアメリカン(インディアン)など多数の、さまざまな背景を持つ人種が混交している。乗組員=人類ということか。となると捕鯨船ピークォド号はノアである。旧約聖書からの引用多数ではあるが、乗組員がのぞれぞれの宗教も大切に描かれる。世界人類の旅の物語。
最後に、ようやく、日本沖で「モビィ・ディック」に出会い銛を突き刺すも、三日三晩の格闘の末、乗組員は一人を残して、みな死んでしまう。生き残った一人は木端に捕まり数日後奇跡的にたの捕鯨船に発見され命をひろう。それが語手「イシュメイル」である。ラストシーンは壮絶でありながら高貴でもある。素晴らしいものを手に入れた。長編小説が持つ豊穣さが素晴らしい。