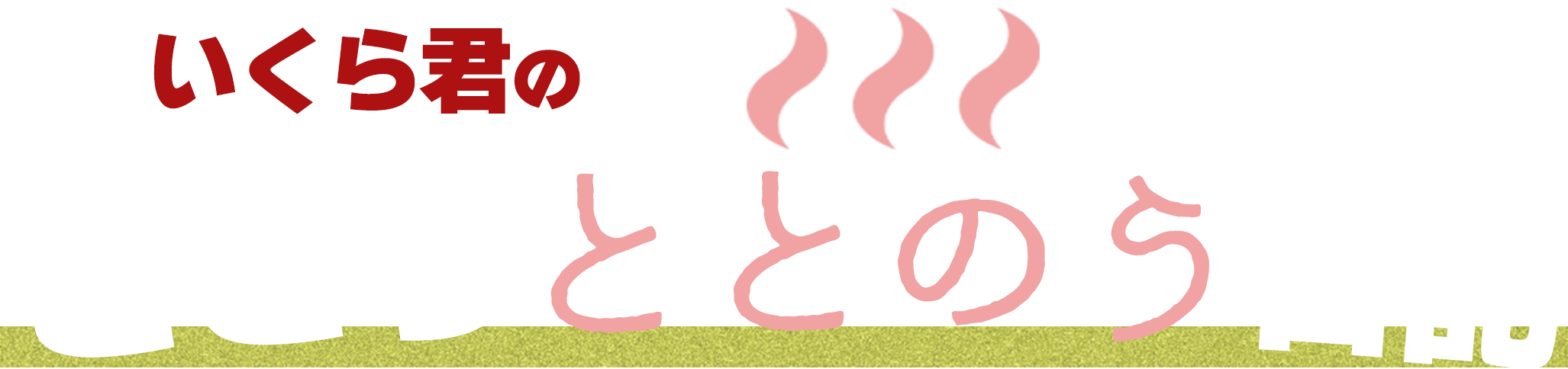斎藤哲也『哲学史入門II』読了

前回に続き、『哲学史入門Ⅱ』読了。ここで扱うのはデカルトからカント、ヘーゲルまで。
第一章 転換点としての17世紀(上野修)。ここでは現代哲学の萌芽ともいうべき、デカルト・ホッブス・スピノザ・ライプニッツを扱う。
第二章 イギリス経験論(戸田剛文)。ここではロック・バークリー・ヒューム・トマスリード、この辺りを扱う。
第三章 カント哲学(御子柴善之)。カントの独特な用語の説明をしつつ三代批判書を扱う。
第四章 ドイツ観念論とヘーゲル(大河内泰樹)。フィヒテ・シェリングを押さえた上でヘーゲルに取り組む。
特別賞 哲学史は何の役に立つのか と銘打ち、山本貴文・吉川浩満と筆者の鼎談である。
前回も書いたが、本シリーズは、人文ライターを称する著者(編者)斉藤哲也が、その道のオーソリティーに聞くという「聞き書き」形式を取る。しかし斉藤氏も哲学に対し相当造詣が深く問題意識も高い。よって彼がな発す質問や感想はその道のプロにとっては、現代的意味も刺激もあるものなのであろうが、「いくら君」のような素人には、造詣の深いもの同士が意気投合しているのを目の前で当てつけられ、不明のまま置いてきぼりにされるような感じがする。レベルの高い人が山の八号目を登っている様子を五号目から見ているような、疎外感のようなものとでもいうか。だからというか、第三章カントの項は、多少カントに触れているため、勉強になったし、彼らが言おうとしていることはかなり明瞭な輪郭を持つことができた。しかし、他のところはイマイチの理解に終わった。不完全燃焼感。
従来の哲学史は、学説を中心に誰がどういうことを考えたのかというかたちで紡がれてきました。でも、新しい学知が生まれるのには、技術や制度が大きく関わっているはずです(267頁)
そうなのだ。本書は「学説を中心に誰がどういうことを考えたのか」ということを並列させるような「従来の哲学史」ではないのだ。そういった過去の形式を踏襲せず、あるいは脱構築した上で新しい哲学史の意味を炙り出そうというのが意図だ。でも、と、「いくら君」は思う。それぞれの学説なり思想の従来の解釈を知らなければ、哲学者同志の関連性・影響などがわからないではないか? やはり五号目までは車で行けたとしても、そこから延々自分の足で歩かなければ八号目も九号目も況や山頂にはたどり着けないだろう。本書では質問者もすでに八号目にいる。五号目の俺はどうなるのだ?
カントの「批判」にしてもヘーゲルの「弁証法」にしても、教科書的な従来の解釈をトップランナーは批判する。しかし、「教科書的な従来の解釈」をよくわかっていなければ、最先端の批判も意味をなさないのではないか。それが、前編通して感じる不満である。