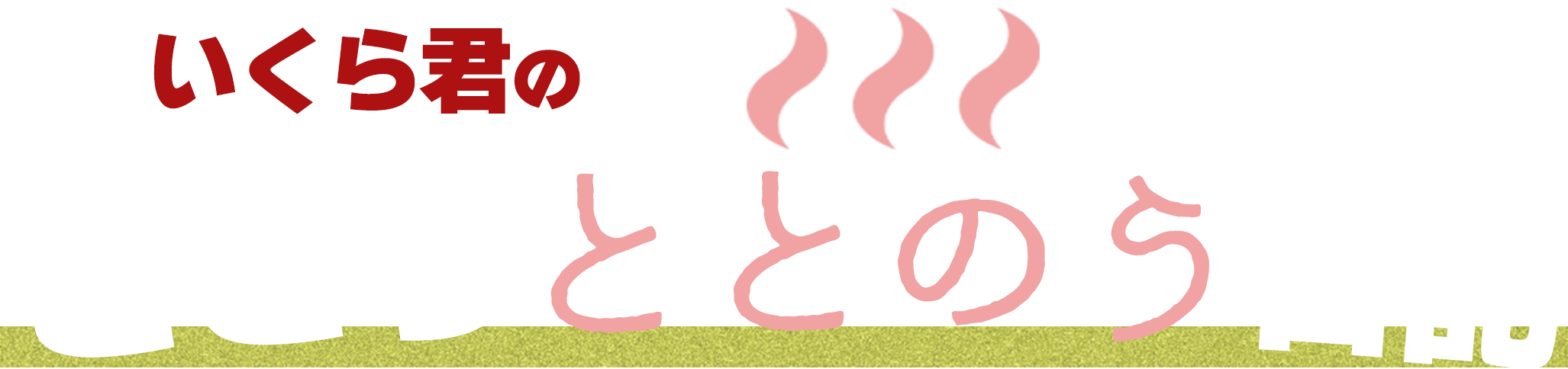高橋源一郎『「書く」ってどんなこと?』読了
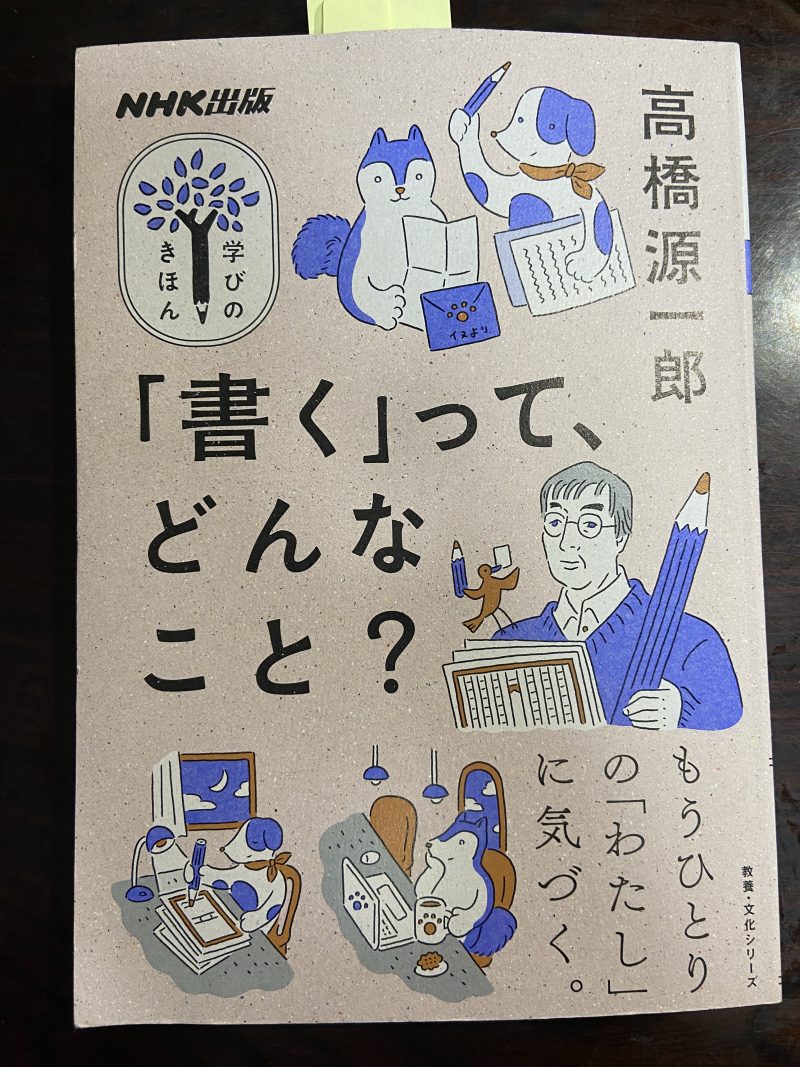
作家であるタカハシさんはもう40年以上毎日文章を書いている。
まず彼はいう。「すべての文章は「わたし」が書いている」、ということを。「かけがえのないたったひとりの「わたし」が」が書いているということ。
そして「考えずに」書く、という指摘。
夏目漱石の「坊っちゃん」という小説は、原稿用紙250枚くらいの作品である。そして漱石はそれを8日から10日で書き上げた。つまり毎日25枚以上。当然手書きである。そしてその原稿はほとんど訂正した跡がないものだという。つまり何が言いたいか。考えながら書いている時間などない。つまり、「考えず」に書いている、と。
さらにタカハシさんは自分のデビュー作になる作品(『さようならギャングたち』)を書いた経緯を教えてくれる。新人賞の最終選考で落とされたタカハシさんは、編集者から500枚の長編小説を書いてみないかと勧められる。しかし、時間は2ヶ月しかない。それでも、彼は始める。まだワープロもない時代である。当然手書き。それを。何者かに取り憑かれたように書いて書いて、1ヶ月で500枚を描き、残りの時間で清書する。ほとんど直すことがなかったそうだ。つまり考えながら書く時間などなかったはずだと。ではその時タカハシさんの中で何が起こっていたのか?
「わたしの中に、「書かれたい何か」、「外に出てみたい何か」がありました。だから何かを新しく作り出す必要はありませんでした。その「なにか」を「外」に出してあげればいい」ということらしい。そして彼は何も考えず一行目を書く。すると一気に一息にするすると言葉が溢れ出し、それをただキャッチして紙に書き付ける人になった、ということらしいのです。彼はいう。「おそらく、このとき、わたしは、生まれて初めて、「書く」ことと接触することに成功したのだと思います」と。
「わたし」の中には「二人のわたし」がいる。「昼間のわたし」つまり「仮面のわたし」。何十年も社会の言葉を吸収した「社会」の検閲を受けたコトバにしか出会えないわたし。「しかし、どうやら、わたしの中には「昼間のわたし」の他に、もうひとりの「わたし」が住んでいるようなのです。ふだんは姿を現さない、夢の中の存在のように淡い、もうひとりの「わたし」です。それを「夜のわたし」と呼ぶことにしましょう。あるいは「ほんとうのわたし」と055頁。つまり社会の検閲を受けていない「コトバ」を生み出すことのできる「わたし」の存在が、ものを書かせている。
「手」が勝手にキイボードを叩いている。いや、「わたし」をすっ飛ばして、「脳」が直接、ディスプレイに「コトバ」を送りこんでいる。「わたし」はただ、それを眺めているだけ。そんな感じです。」063頁
こんなに楽しい時間はないだろう。いわゆる、ゾーンに入ったというやつか。2024年9月における大谷くんのような感じだろうか。そのとき大谷くんは「今の打席」にすべての集中を向けられる状態にあったのだと思う。「ああ、今ホームランは何本だから、ここでこうすると、記録だなあ。とかここで盗塁すると、新記録だなあ。」なんてことはおそらく全く考えていない。ただただ、「今こん打席で自分にとってのいいバッティングをする」ということだけに集中している。
いくら君も、昨年の秋に書いた「リスト」の中でそうのような経験をした。もう描きながら、あたらしアイディアが次々に浮かび、楽しくて仕方がない。アドレナリンドバドバ、みたいな感じ。(まあ、いくら君のその作品は仲間内でボロボロにされ、新人賞に応募するも一次選考すら通らなかったのですが)
社会の検閲を受けない、「もうひとりのわたし」の言葉で書く。難しいことではあるが、「コトバ」に対しての、あるいは「書く」ということに対しての新しい所見を示され、盲を開かれた感がある。いや、さすが高橋源一郎!離婚四回、結婚五回の男は、飄々をしているようで、実は実にエネルギッシュでもあるのですね。いい本でした。