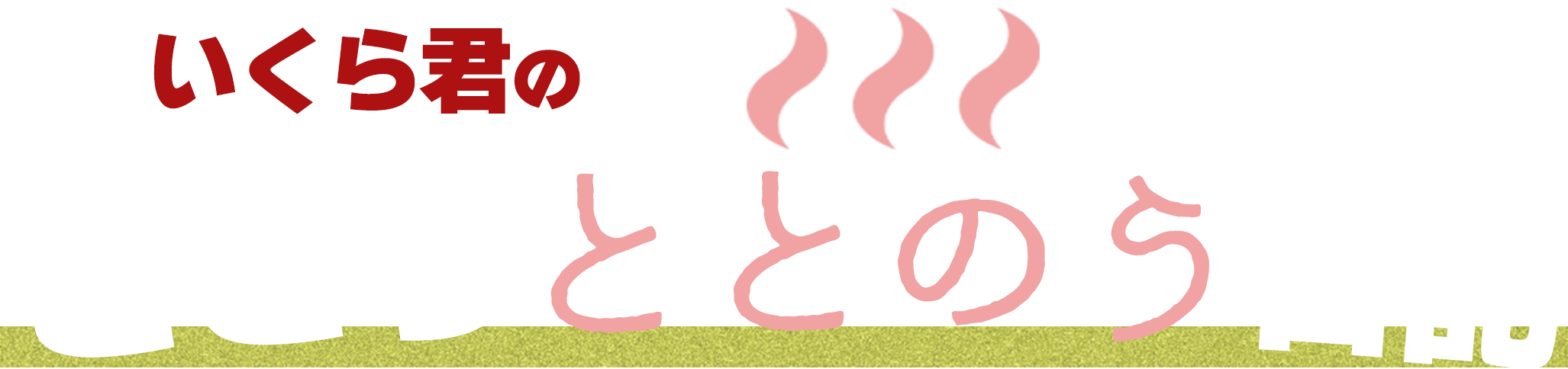川端康成「眠れる美女」読了
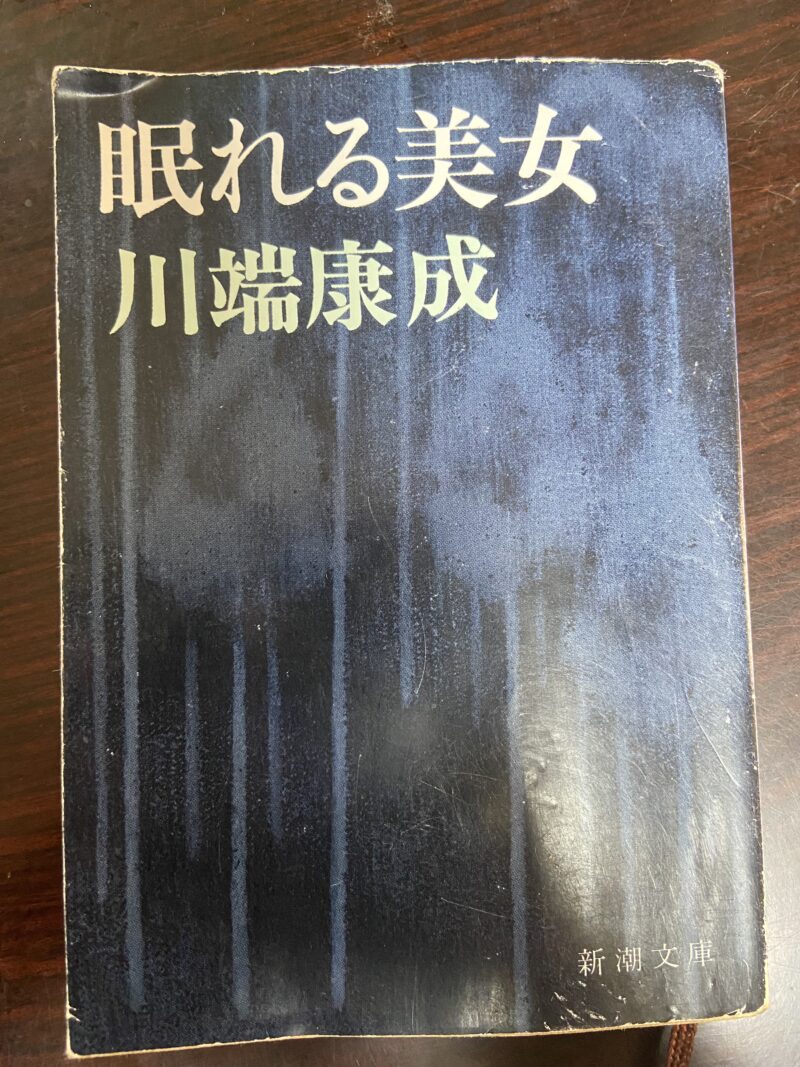
こりゃ、やばい。相当やばい。
〈川端康成〉。言わずと知れた、ノーベル賞作家である。美しい日本語の使い手であり、抒情的な物語の名人である。
本作も、美しい日本語で描かれた切ない物語だが、その奥に男の、老人の絶望的な悲しみがある。ああ、とうとう、いくら君もこの境地に近づきつつある、ということなのだ。
漱石も芥川も太宰も三島もみんな若くして死んだ。つまり老人文学が作品群に存在しない。老人の性を扱ったものとなると、寡聞にて谷崎くらいしか知らなかった(「瘋癲老人日記」「鍵」等々)。でも、川端のエロさは、谷崎の変態をうわまっているのではないか。変態が変態らしく行動するより、常人の奥に眠れる矯められた性の方が、それも不能になったのちの観念としての性の方が、エロいと思う。
67歳になる江口老人は、友人から教えられた館を頻繁に訪れる。そこは、すでに男としての機能を失った老人のための逸楽の館であった。真紅のビロードのカーテンの奥には、薬物で眠らされ、絶対に目を覚まさない美少女ーー彼女と老人は一晩添い寝をする。江口老人は眠れる美女と添い寝をしながら、自身と語り自身の過去と対話する(当たり前だが、寝ている人間と会話はできない。よって若さを当てられ自己省察するしかない)。若い肉体を目の当たりにするということは、いやがおうにも自らの醜い老いを突きつけられことになる。江口老人の若い娘に対する視線は執拗である。とうとうねちっこい。熟れすぎた果実酒の芳香で、我々読者は陶酔し、蠱惑的な死を予見する。まさにデカダン文学の真骨頂である。本当に驚いた。
もし、三島が生きていたら七〇歳くらいで老人の性を描いたかもしれないが、上述のように昔の文学者は若くして死んでおり、残っていないのが、残念だ。
現代ーー我々のたつ地平は、政治も経済も文学もみな表面の世界で席巻されてしまっている。リアルなものでなく作り物のツルツルな世界。裏側は禁止され闇に沈静しネットの中で蠢くしかない。
今、著名な作家はこういったタイプの作品を書かないだろう。テーマにないのではなく、社会的な忖度というか配慮から。もしかしたら、自分の名声が全て台無しにされる可能性があるから。
あるいは、やはり、川端のエロスと感受性と描写力が突出していたということなのかもしれないけれど。