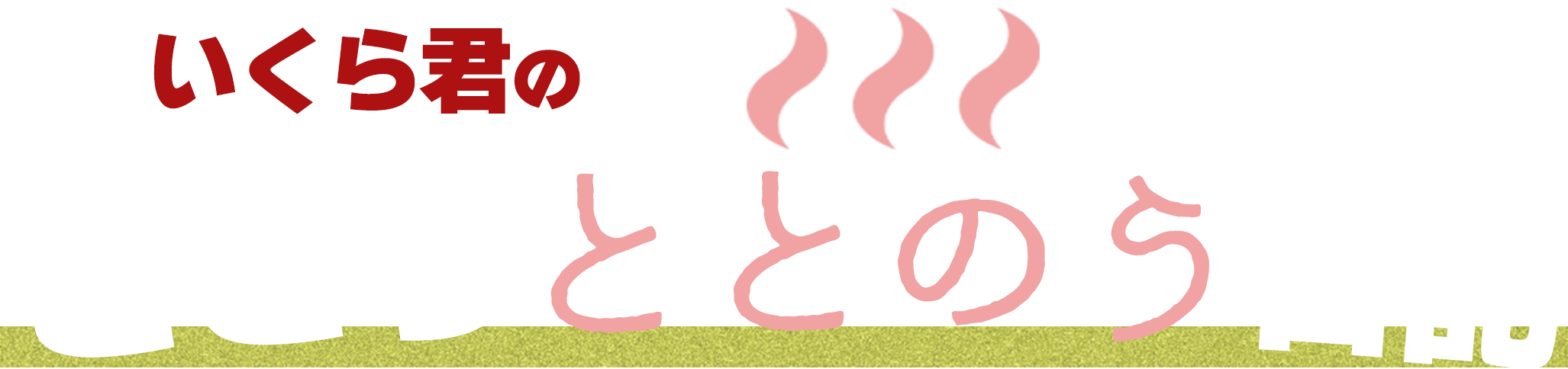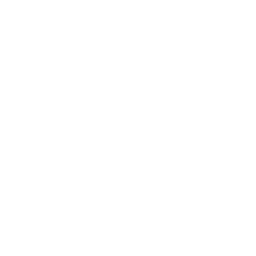竹田青嗣『はじめてのフッサール『現象学の理念』』読了
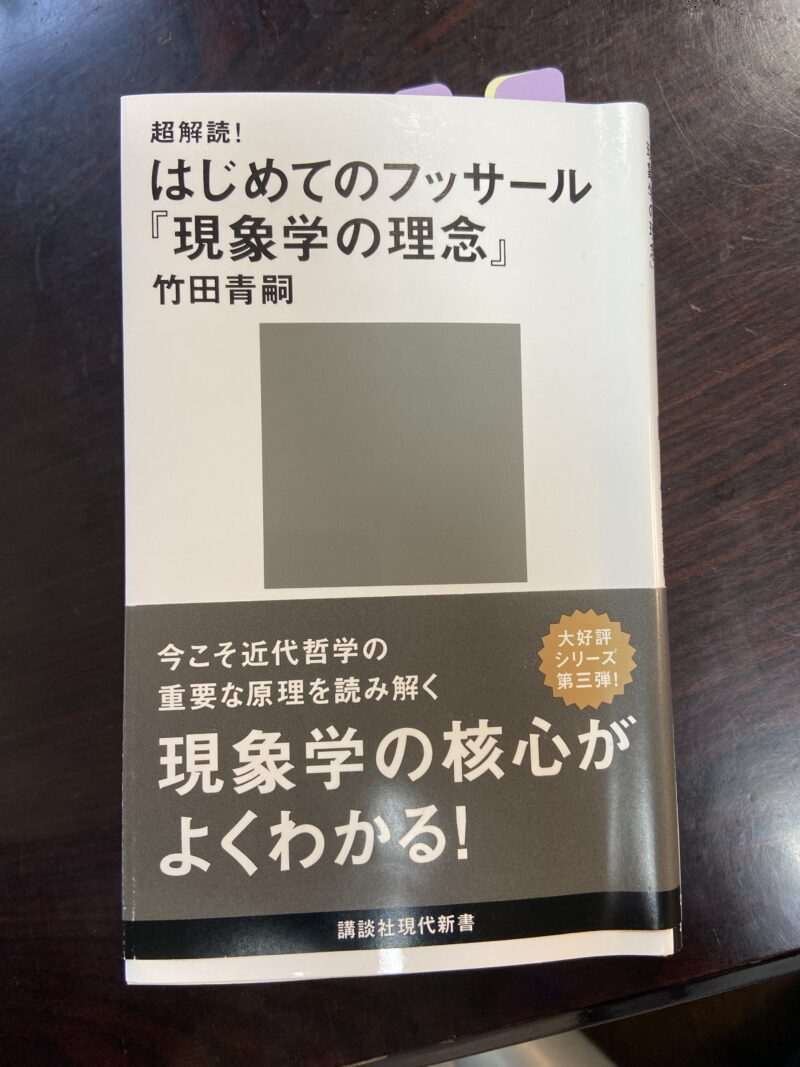
今年初めの、哲学的取り組みは「現象学」とする。
まずは手始めに、竹田青嗣のフッサールから。
現象学の概念を把握するのは、いくら君にとって至難である。大昔からずっと気になっていた。そこで、少し手を出してみる。しかしよく理解できず討死する。そんなことの繰り返しであった。で、竹田氏の登場である。彼の哲学がの理解は幅も厚みもすごいものがある。昔は文芸評論家という肩書きであったが、今は哲学者というところなのだろうか。(柄谷行人が言うように、近代文学の大きな役割はもうすでに終わってしまったのだろう(『近代文学の終わり』)。よって、文芸評論は見向きもされない過去の遺物になってしまった。
閑話休題。
フッサールである。現象学である。
竹田氏による。古来哲学における問題は認識論であった。主観ー客観の一致は可能か、不可能か? 哲学者たちはその問題に取り組み、解決することができなかった。そこでフッサールはいう。「主観ー客観」図式を方法的に中止し(エポケー)、別の図式をとる、これを「現象学的還元」と言う。しかし、この図式がわからない。フッサールの言いようも、わかりにくい。そこで竹田青嗣の登場だ。
「現象学的還元」は、まず客観が存在するという「措定」、つまり前提を中止する。そして全てを自分の「意識体験」に「還元」する。すると、世界の存在の全ては、自
分の「意識」に生じている”表象”でる、と言うことになる。(21頁)
枠組みは、わかった、と言うことにしよう。しかし、わからない。竹田氏が丁寧に繰り返し説明してくれるにも関わらず、その論拠は雲を掴むような、あるいは砂上の建築物のような、あるいは蜃気楼を追いかけるような、作業となり、掴んでも掴んでも指先から逃げていく。
こんな状態で無謀とも思えるが、これ以降、原著『現象学の理念』に突入する。