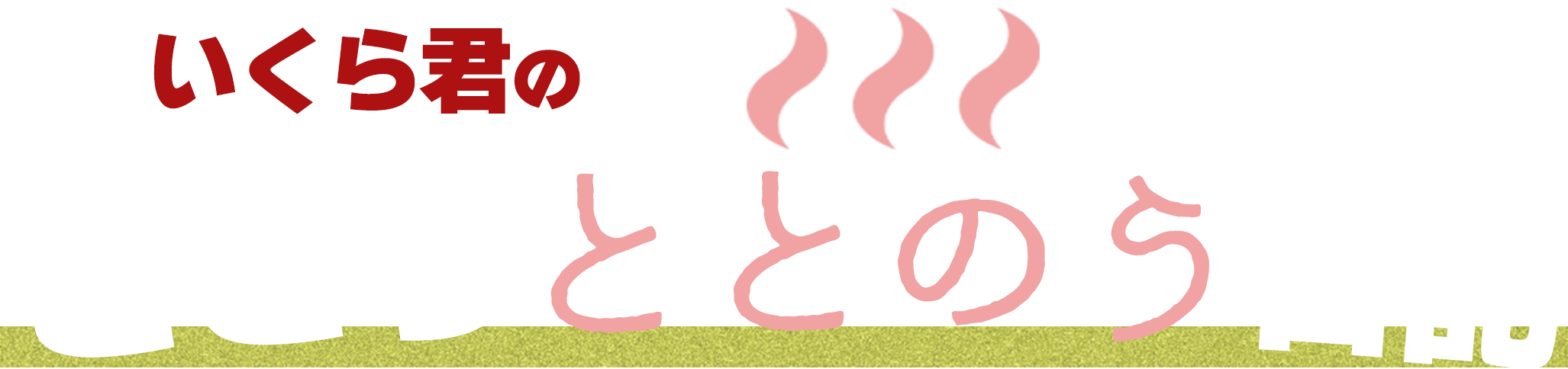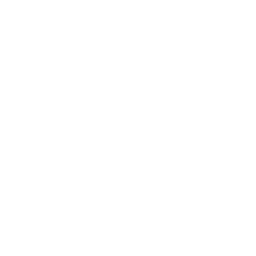ニーチェ『善悪の彼岸』読了
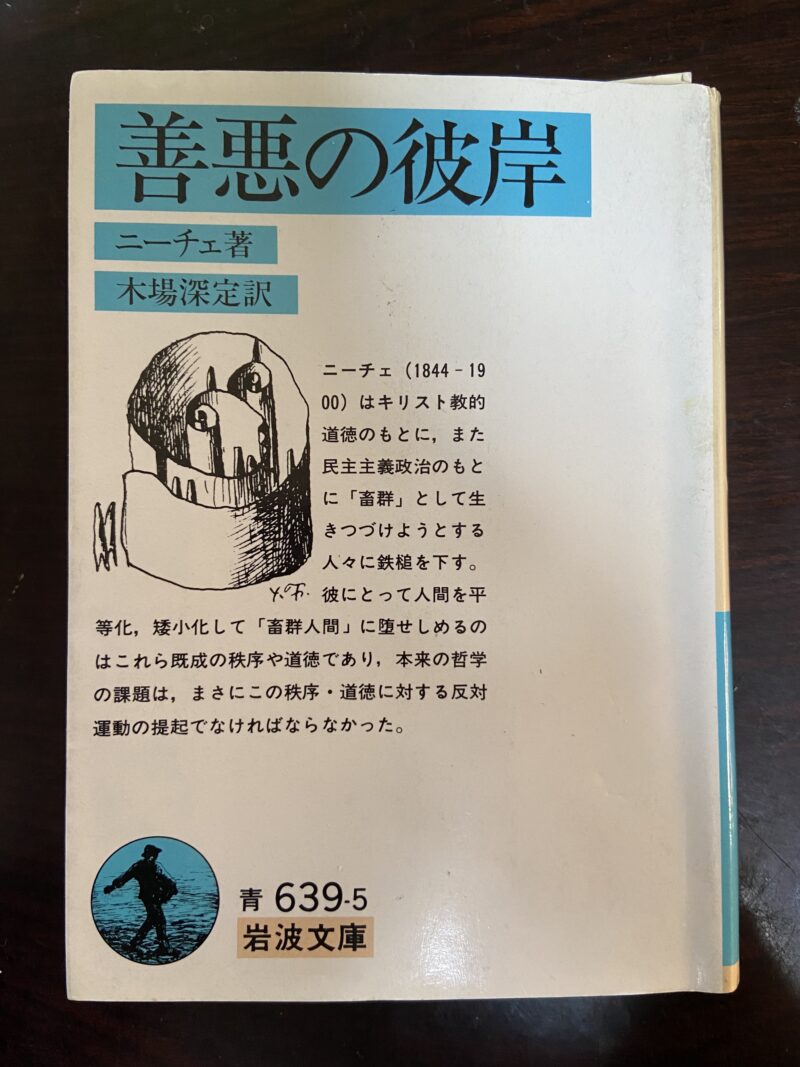
とうとう、ニーチェに入った。
昔から、気になっていた哲学者である。ツァラつストラに挫折して以来、数十年ぶりの再挑戦となる。
色々西洋哲学を学んできて、どうしてもニーチェは避けられない。挑まなければならない。調べると多くの評論家は最大の傑作は「ツァラつストラかく語りき」であるが、いきなりは難しく、まず「善悪の彼岸」と「道徳の系譜」を押さえて後、「ツァラツストラ」に挑むのが良い、とのことであり、今回『善悪の彼岸』(木場深定訳 岩波文庫)にチャレンジしたという次第であります。本作は全体、断章といった感じの比較的短い文章から成り立っており、一つの大きな論理構造としての伽藍を目指したもの(カントをイメージしている)というより、エッセイ風の断章を積み重ねているというものである。
ニーチェによって現代哲学が始まるといっても過言ではあるまい。西洋哲学はソクラテス・プラトン・アリストテレスなどのギリシア哲学に源流を持つが、その後世界を席巻したキリスト教と切っても切れない間柄にあるといえよう。中世の黒い圧の下から、ルネサンス・近代科学・デカルト・カントを通じて少しずつキリスト教の精神的支配から逃れようとした歴史があるが、それからの呪縛を徹底的に破壊したのがニーチェであるといっても過言ではないだろう。
まあ、とにかくディスるディスる。キリスト教という毒を、民主主義社会を権威を意外を。いずれも既成の秩序を破壊することに努めたのが彼の恐ろしいまでの執念なのである。
「善悪の彼岸」。つまり、善や悪と言われ人心を制御しているものの彼岸つまりあちら側、というのがタイトルの意味である。全体、アフォリズム的断章でそれまでの既成概念を権力者を次から次へと薙ぎ倒していくのだ。その根拠は類稀なる知性に裏付けられている。
読んでいる最中に書店の納品書に気づいた。それによると本書購入は平成2年七月とある。35年前? やはり本は偉大である。命が長い。