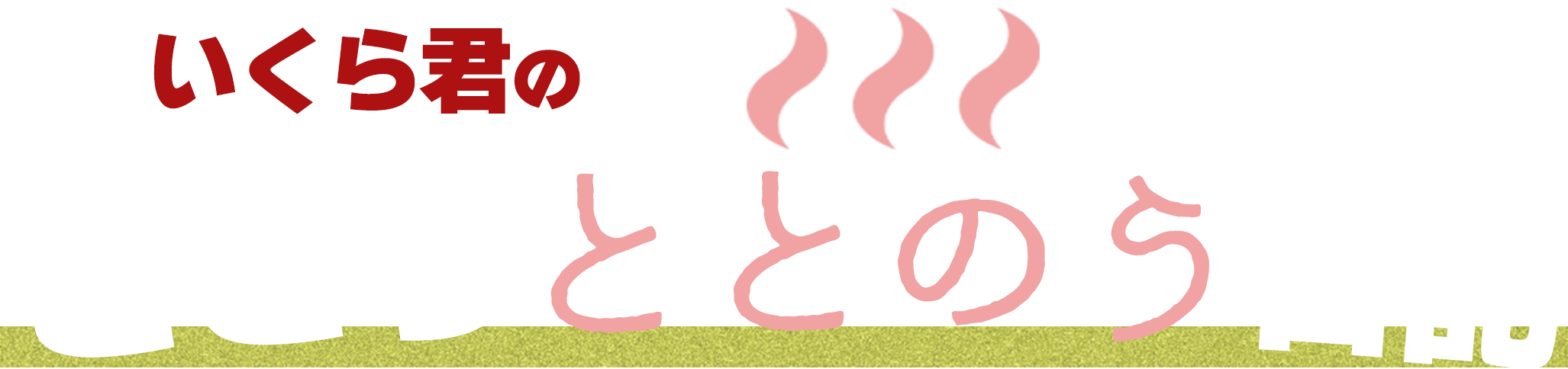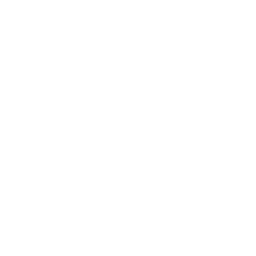川端康成『みずうみ』読了
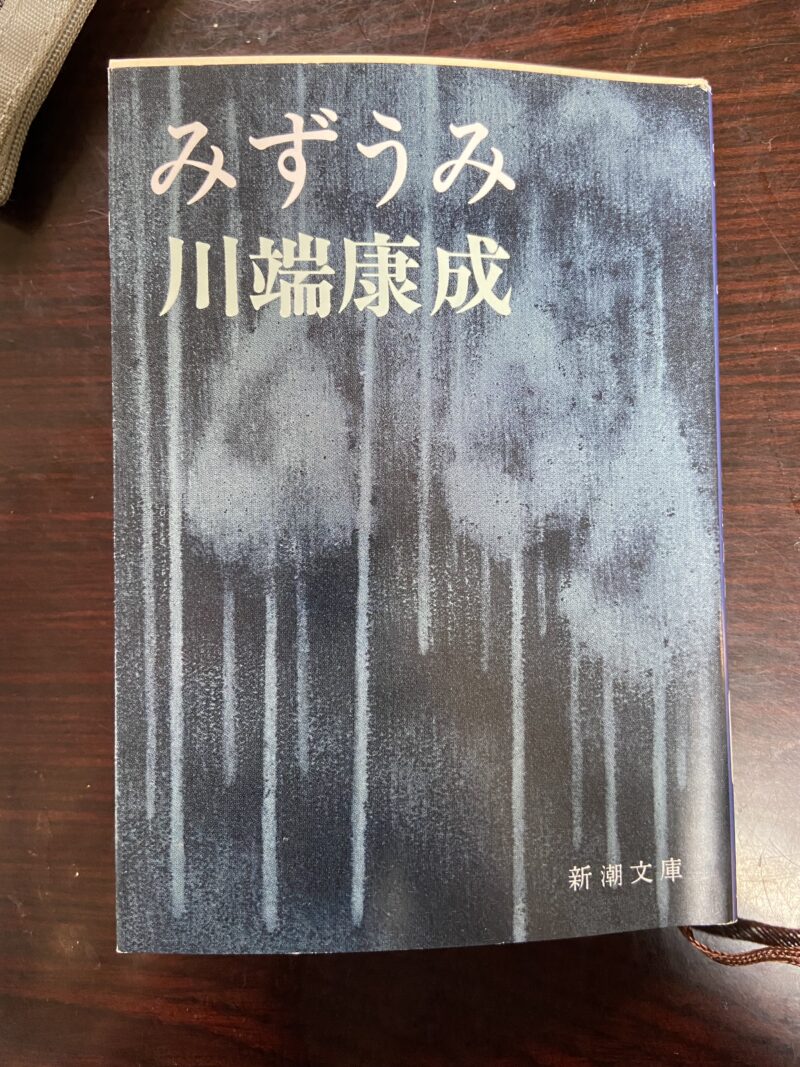
なんとなく昔から本棚の端にあった。
「伊豆の踊り子」でもなく「雪国」でもなくい「山の音」でも「千羽鶴」でもなかった。川端の作品群では傍流にあたるのだろう。それをほんも気まぐれで手に取った。最後のページを繰って出た言葉は「なんじゃ、これや?」であった。
本作『みずうみ』は1954年から翌年にかけて「新潮」に連載され、単行本化された作者五十五歳時の作品である。もうこの時点ですでに川端は社会的名声を獲得している。だから実験的な(投げやり?)な本作を描くことが許されたということなのか?
視点人物は二人、あるいは柱となる人物は二人と言い換えようか。まず「桃井銀平」。彼は女子高生の教え子を、今で言うストーカー行為をし、恋愛事件を起こして教職を追われる人物。その桃井が気まぐれで跡をつけた女が「水木宮子」で、彼女は金満か老人に囲われる身であり、魔性の魅力を放ち、よく男につけられる。物語の初めは、宮子がストーカー行為をした銀平をハンドバッグで殴り逃げ出す。ハンドバッグには二十万円入っており、教職を追われ持ち金のない銀平はその金を持ち軽井沢を放浪する。軽井沢の湯屋(トルコ風呂)の女とのやり取りから話は始まる。
場面をかえ、ストーカー行為をされた宮子の視点になり、彼女と彼女を書こう七〇歳間近の老人との会話に話は移る。また、視点は銀平に戻り、教え子との変態的恋愛や幼少の頃の記憶など銀平の意識の流れのままに物語は展開する。意識の流れに忠実に話を書くと、時間軸は曖昧になり過去へ行ったり現実へ帰ったりとする。
全体を通して流れるのはデカダンスの腐った甘い香りとでも言おうか。しかし、本作は強い計画の元に書かれたものではなく、また、一貫した何か柱のようなものを持ち合わせておらず、海鼠のようにうねうねとして掴みづらい。フランス文学の影響なのか、意識の流れを中心に書けばそうなるのは必然だとしても、終わり方はあまりに唐突というか、無責任というか、悪く言えば、面倒くさくなって途中で放ってしまったような印象さえ持つ。いかがなものか?