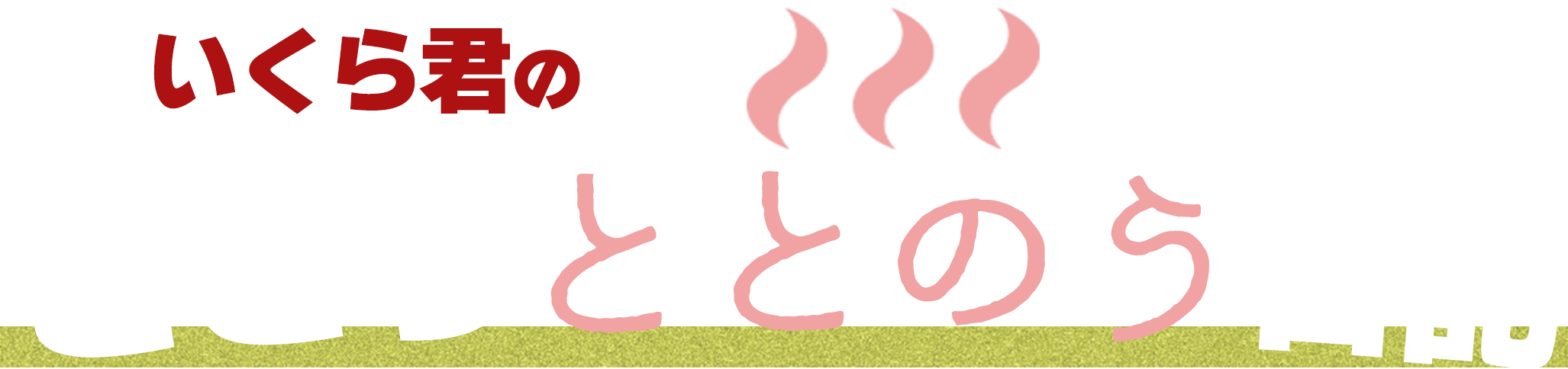川端康成『雪国』読了
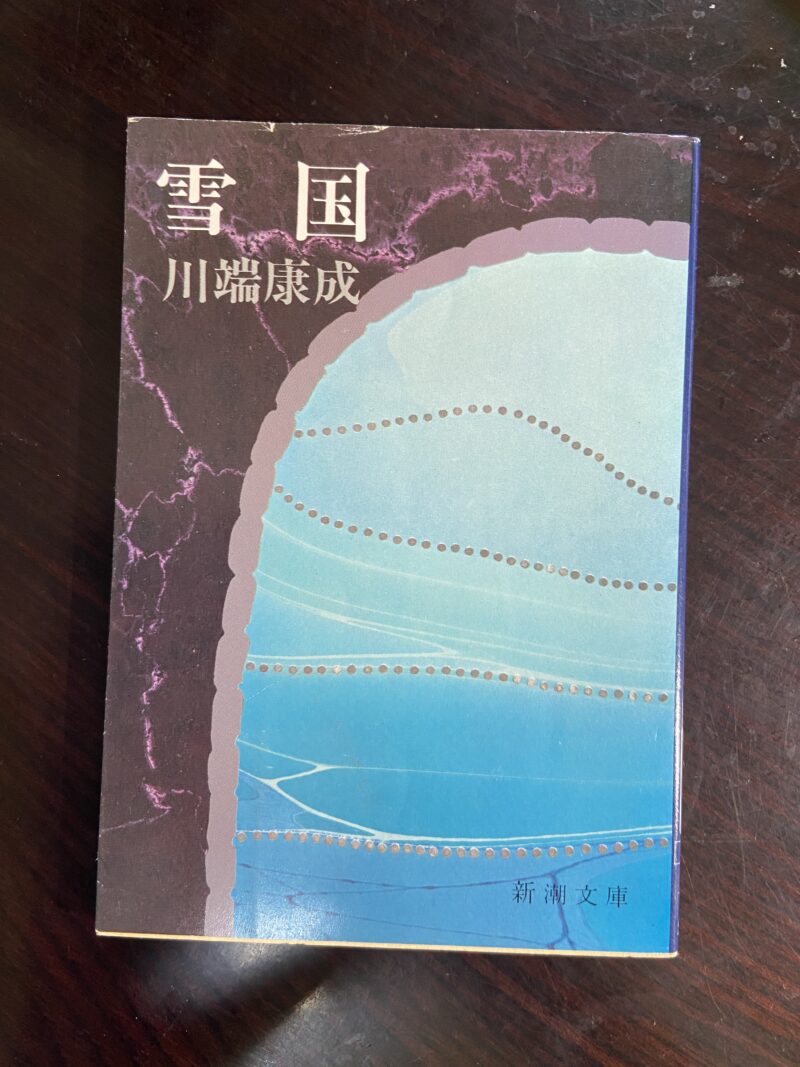
文学を志して50年。
恥ずかしながら、「雪国」を今まで通読したことがありませんでした。もちろん何回か挑戦したことはあります。しかし、どうにも川端の新感覚派的手法(なんていうのかな感覚的なんですとにかく。説明なく跳ぶんです。意識の流れってやつですかね)についていけず、イクラくんが物心ついた頃にはもうノーベル賞作家であり、大先生であったにも関わらず、川端作品は読まずに(読めずに)いました。やはり太宰から入り、一応漱石を抑えてから、性に目覚めたイクラくんは三島・谷崎と深入りしていったのです。そこには川端の席はありませんでした。大学では越後湯沢出身の小堺くんだけが川端をやってました。
で、最近、「眠れる美女」の世界にハマり、ちょくちょく川端作品を手に取るようになったわけですが、若い頃はわからなかった男と女の情みたいなものが少しわかるようになってきた、というか、腑に落ちるようになってきたのです。読めるとわかる、川端の偉大さ凄さヤバさ。
冒頭部は子供の頃から知っていました。超有名な始まり。
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」
完璧な始まりです。ここで黒から白へ都会から田舎へ。一気に世界を反転させる仕掛けを提示します。そして、読者をこの世界観へ導くまでの大変ナイーブな部分、具体的に言えば、座席の目の前の女性(葉子)と病人の男そして、凍えた窓ガラスに移る葉子の美しい姿とガラスの向こうの景色が交差する部分。ここの描写は本当に素晴らしい。繊細な状況を繊細なタッチで、丁寧に、でも投げやりに描く様子が目み浮かぶようです。作者もかなり苦労したのではないかな? 何度も何度も書き直したような気がします。
そして駒子との再会と、過去へ戻って出会いの場面。ここまでが世界観を読者に伝えるなかなか手ごわい場所だと言える。
その後は割と手慣れた感じで、感覚的に理屈をすっ飛ばしながら駒子の情熱と男の感動や不感症な冷めた視線・悲しみ・空虚、そして葉子への関心とラストの火事のシーンと進みます。どこまでも繊細でナーバスで男と女の機微で満載でした。
割と最初の部分で島村が左手の人差し指を突き立て、これが駒子を覚えていた、というあたりは、まあ、なんとえっちなのでしょう!と、いいおっさんのいくらくんでも頬を染めたくらいセクシーなのでした。
ああ、これから、ちょっと川端を真剣に研究しなきゃならないなあ。
これは、長い歳月と、情熱と空虚、あるいは大変な贅沢が昇華された結晶のような作品でした。