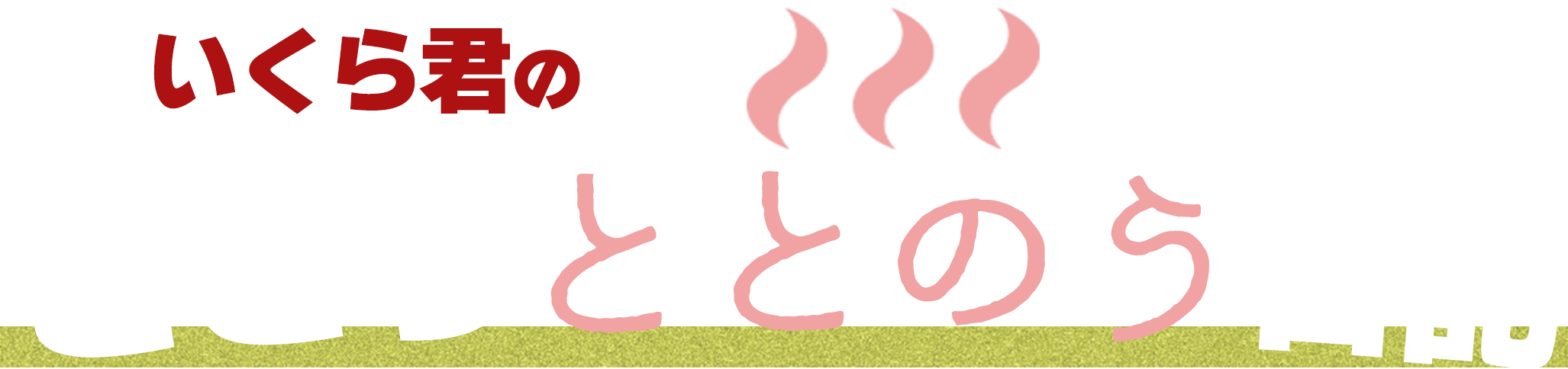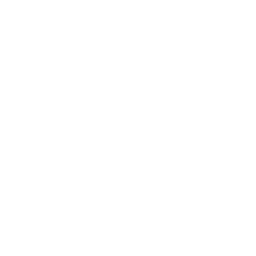出口智之『森鷗外、自分を探す』読了
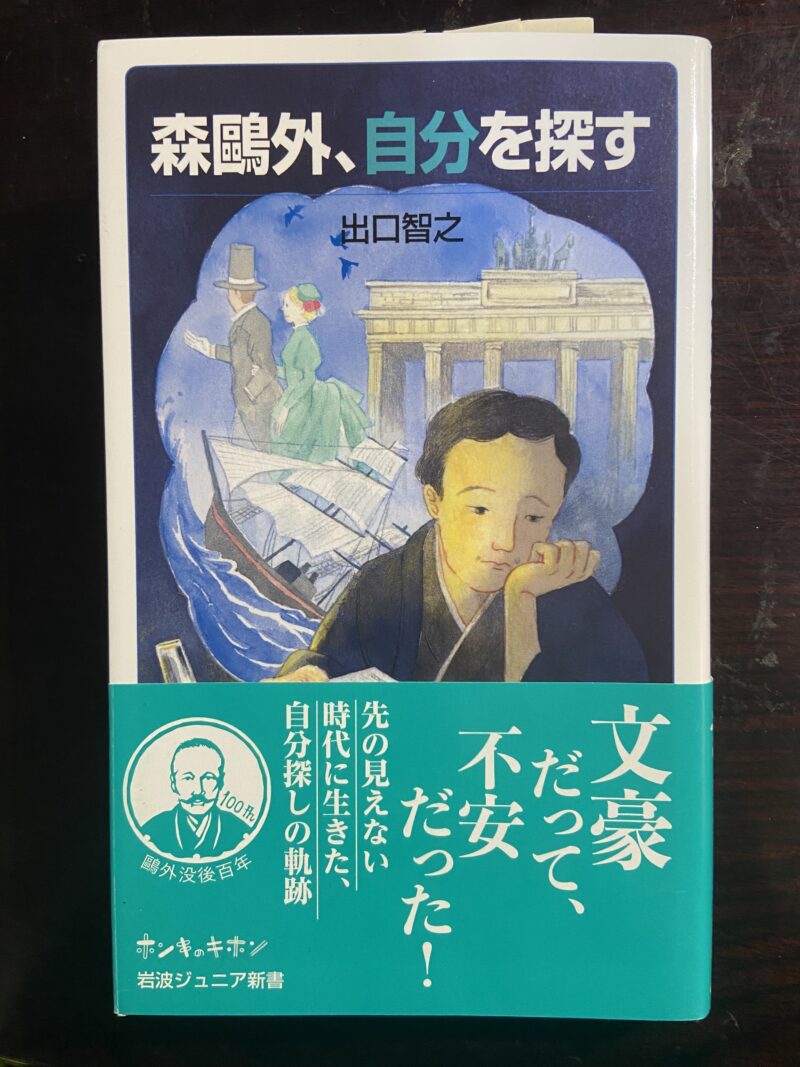
昔、若い頃、漱石と鷗外が明治の二大巨頭として並び称される理由が今ひとつわからなかった。両者とも明治初期に西欧に留学し(鷗外はドイツ、漱石はイギリス)に、先進知識のみならず、近代的個人主義的思想を身につけ帰国し、古い体質のままの日本の慣習と戦いながら、最前線の知を啓蒙する、また、華々しい学歴など、共通する面は多々あれども、全身小説家である漱石に対し、鷗外の小説は少なく、また、歴史小説など晩年は誰も読まないようなものを残す、文学者というより知の巨人のイメージであった。また、作家になるため宮仕をさっさと辞めちゃう漱石に対し、陸軍の軍医として最高峰を極め、軍事引退後も、文化的分野において宮仕をし続けた鷗外。人間的な漱石に対して、あまりに出来杉くんの鷗外。小説家としての印象が、若い私にとって、鷗外はあまりに薄かった。
もちろん、私なりに齢を重ね、勉強も深まるにつれ、人としての鷗外が見え始め、二大巨頭と称されるのは当然であり、というより、その二人が明治時代において、近代日本の精神的支柱としてあまりに突出していたことを肌で感じるられるようになったのである。
そして、本書に出会う。最初「岩波ジュニア新書」の「ジュニア」に引っ掛かりを覚えながら頁をくり始めたものの、そんなことはすぐに忘れ、筆者の見識、ものの見方、資料を駆使した執筆の姿勢に、刺激され、私の中での新しい鷗外像がさらに焦点を合わせクリアになってきたのだった。
ものの始めは「舞姫」の扱いである。私も晩年、国語教師として「舞姫」の扱いには苦慮した思いがある。まず、若い教員がやりたがらない。生徒が、主人公太田豊太郎を、頭はいいけど、優柔不断で女を孕ませたものの捨ててエリートコースを選択する極悪人としての読み一択である点(特に女生徒)。私が授業で性的な話題に触れ、女性と2名によって、勤務する神奈川県教育委員会に苦情が挙げられたこと、など今までの授業のあり方では、なかなか通らない現状に困惑したのである。私が早期退職した理由の一つが「舞姫」であったことも事実である。
筆者は、この「ダメ人間豊太郎」の読みを、懸命に現代的視点を取り入れながら、若者たちを納得させる形で、豊太郎の名誉を回復させる、あるいは、さらに深い読みを提出する点に大いに力を得ることになった。さらに、エリーゼに関する旧弊な社会との葛藤、一人目の妻との葛藤、陸軍人としての小倉時代(左遷?)の葛藤、二人目の妻と母親との、嫁姑問題の狭間での葛藤、といった生活面での苦悩がありながらも、一方で役人としての栄誉を極め、また作家・文人としてのレベルの高い大量の仕事、また、妻からの愛され方、あるいは、子供たちからの愛され方、など、鷗外の人生の濃密さに驚くとともに、律儀さに感心しながらも、最期「石見県人、森林太郎として死す」、つまり、一才の肩書は虚飾であり、私は一個人として死ぬのだ、という強いというか、寂しいというか、の宣言、とうとう、驚きの連続で、大変勉強になった。
筆者は1981年生まれの東大の准教授。オレよりの二十歳若い。嗚呼。