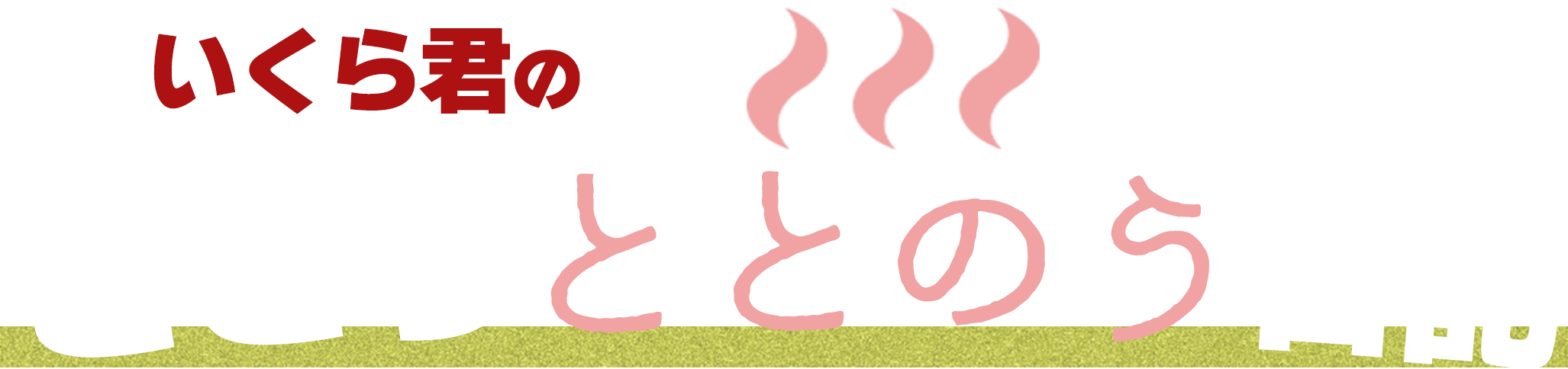中村文則『土の中の子供』読了
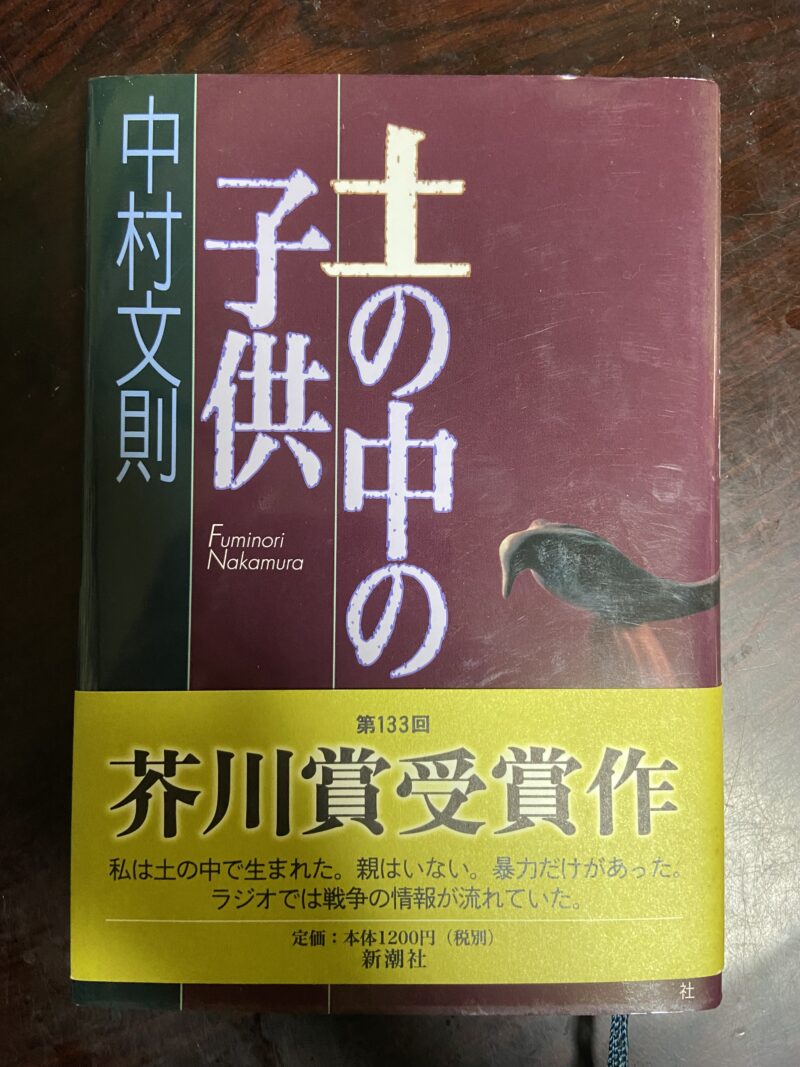
最近、過去の芥川賞受賞作を追っている。
中村文則はずっと気になっていた。読んだことがないのに、どこからどういう情報が自分の中に入っているのか見当もつかないが、中村はいつかは読まねばならない作家だと確信していた。すでに何作か著作を購入していた。が、私の中の何かが熟していないというか、読まないで?読めないで?いた。
今回ようやく、本作を手にすることになったのだが、やはり、いい、というか、すごい。彼の中にあるなんとも形容もつかない「何物か」をつかもう、と言うか、抉り出そうというのが、彼の文筆活動なのだろう。自分の心に、誤魔化しなく、誠実に、糸で釣った錘を落としていく。それは、徐々に深いところへ降りていく。そこに何があるのか、何が見えてくるのは、誰にもわからない。もちろん、本人にもわからない。でも、それを馬鹿みたいに誠実に行うことが「文学」なのであろう。
親に捨てられ、里親に散々暴力を振るわれ、施設で育った「私」。根本に大きな問題を抱え、生きづらい中を生きている。彼は死なない。死のうとはしない。つまり自分から逃げない。
同居人の白湯子。彼女も、キャバクラで働きながら、捨てられた男の子を死産で産んだことから離れられないでいる。その時からセックスに感じなくなった。白湯子が酔っ払って大怪我をする。治療費が必要だ。施設で世話になった「ヤマネさん」に金をかり、サボりがちだった仕事(タクシー運転手)も真面目に取り組み始めた矢先、タクシー強盗にあい、かろうじて命拾いしタクシーで逃げるものの、ふわっと、誘われるように、ガードレールに突っ込み、大怪我をする。白湯子と同じ病院である。白湯子は松葉杖をつき、懸命に献身的に「私」の世話をする。
「私が望んでいたのは、克服だったのではないだろうか。自分に根付いていた恐怖を克服するために、他人が見れば眉を顰めるような方法ではあったが、恐怖をつくり出してそれを乗り越えようとした、私なりの抵抗だったのだろう。」95頁
病院で意識が戻った後、白湯子は「私」を責める。
彼女の目は厳しい。唇を震わせながらいつまでも視線を逸らすことがなかった。私は目を閉じたが、眉間に力がこもるのを、止めることができなかった。
「わからないんだよ」私は、正直に答えた。「ただ……、優しいような気がしたんだ。これ以上ないほど、やられちゃえばさ、それ以上何もされることはないだろう?世界は、その時には優しんだよ。驚くくらいに」
「何言っているのよ。意味がわからないよ。それに、それって、死ぬってことじゃない。死んでどうするのよ」
「似てるけど、違うよ。違うような気がする。それと…」そういったとき、私の声は震えた。「ぶつかっていく間、すごく自分に自分が合わさっていくような気がした、止まらなかった」
「馬鹿」
彼女はそういうと涙を流した。
「どこまでも相手するって言ったじゃない。嘘をついたの?酷いじゃない。こんなの、卑怯だよ」
「そうだな、ごめん』
(中略)
「なんだか泣きたくなってきたよ」私がそう言うと、彼女は笑った。
「…泣けばいいじゃない。ここには私しか、いないんだから」 100頁
ラスト。「私」はヤマネさんに池袋で待ち合わせをする。父親が会いたいと言ってきた。初めにそういうと、「君」は来ないと思ったから。と、弁解をする。しかし、丁寧に「私」は挨拶をし「僕は、土の中から生まれたんですよ。」「だから親はいません」と言って背を返す。
二人が通じ合えた時、いくら君は慟哭した。なぜ、こんなにも心が震えるのだろう? この小説の中に何が埋まっているんだ? いや、この小説の中に埋まっている何かに反応する「何か」が俺の中にある。俺の中にあるのはなんだろう? 何か変なものが俺の中にいる。蠢いている。確かに。しかし、姿を見ることはできないし、言語化することも、イメージすることもできない。
残されたわずかの時間で俺がやらねばならないことは、この俺の中にある「なんか変なもの」の正体に近づくこと、になるんだろうな。