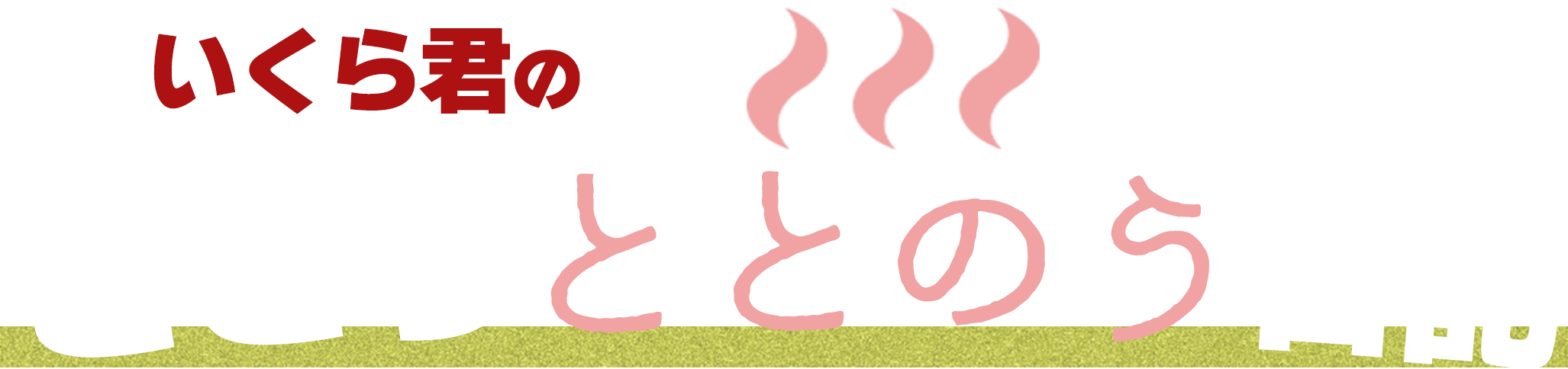ラディゲ『肉体の悪魔』読了
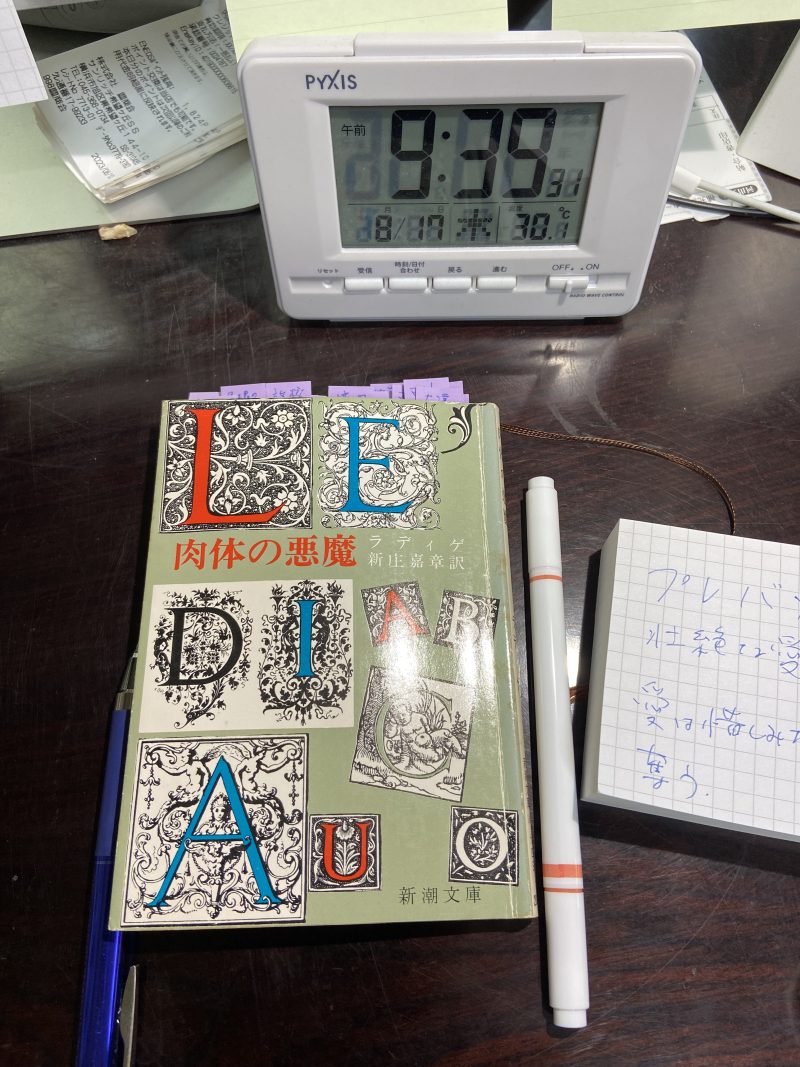
前回に続いて、ラディゲ。処女作『肉体の悪魔』。訳者新庄嘉章の「あとがき」によると、『肉体の悪魔』はレイモン・ラディゲが、十六歳から十八歳の間に書かれたものとされている。本作が処女小説だというのであるから衝撃である。周知の通り、ラディゲは一九二三年、二十歳の時に亡くなっている。早熟の天才と言って誰も異論を挟む余地はないだろう。
場面はフランス・パリ、およびその近郊の自然大き場所。主人公たちはマルヌ川のほとりのF・・・町に住んでいる。主人公は高校生(途中で中退)の「僕」(15歳〜16歳)と、知り合って間も無く結婚する「マルト」(19歳〜20歳)である。彼らは愛し合い、第一次世界大戦に出征中の夫ジャックがいないのをいいことに、逢瀬を繰り返し愛を極限まで深めていく。
ただの世間から祝福される愛ではない。手垢まみれのこんな言葉を使うのも不愉快だが、いわば「不倫」である。順調に親や友人が代表する「世間」と握手しながら愛を深めていくものとは異なる。「僕」は「マルト」を愛せば愛すほど、もちろんこれには、精神的意味だけでなく、肉体的な快楽も含まれている、出征中の夫を意識せざるを得ず、「マルト」はマルトで、世間から認められている夫との関係を完全に断ち切ることもできず、休暇で帰ってくる夫を受け入れる、つまり、二人を宥めるために多くの嘘をつかざるを得ない。嘘を知る「僕」は「マルト」を嫉妬の力で激情的に責め、なじり、すぐさま嫌われる恐怖から、自分の態度や暴言を反省し、愛の証明を懇願し、また接吻から…。その繰り返し。ただただ苦しく、自分を縛り、彼女を縛り、誰にも認められない、二人だけの、危険なガラス細工の愛に溺れていく。
『肉体の悪魔』は『ドルジェル伯の舞踏会』と違い、一人称小説である。厳密に考えれば、一人称小説は主人公「僕」以外の登場人物の内面はわからないはずである。よって、自分以外の心理を描く場合、セリフにするか、主人公の推量にするしかないはずだ。しかし、ここでの「僕」は自分の内面だけでなく、断定の形で「マルト」はじめ、他の登場人物の心理も細やかに分析する。その筆が非常に冷静で、青年期にありがちの自己陶酔的な甘えはない。冷静で合理的。不合理なエゴイズムに見える「僕」や「マルト」の突飛な言動をも自然に我々読者に納得させてしまう力がある。
さらに、時に挟まれる箴言。
「子供はなにかと口実を考えるものだ。いつも両親の前で言い訳をさせられているので、必然的に嘘を着くようになるのだ」
まさに。首肯す。
過去にこんな厳しい愛の淵に陥りかけたことがあったような気がする。それは純粋であればあるほど困難で厳しく切ない。そして、その場を取り繕うために、「嘘」をつく。そしてその嘘が自分の純粋性を侵すことになる。嫉妬を呼び込む。罵倒する。それが、性愛の妙薬にもなることを途中で覚えてしまう。なんという無限地獄!
素晴らしい作品である。
次回は、ラファイエット夫人『クレーブの奥方』。