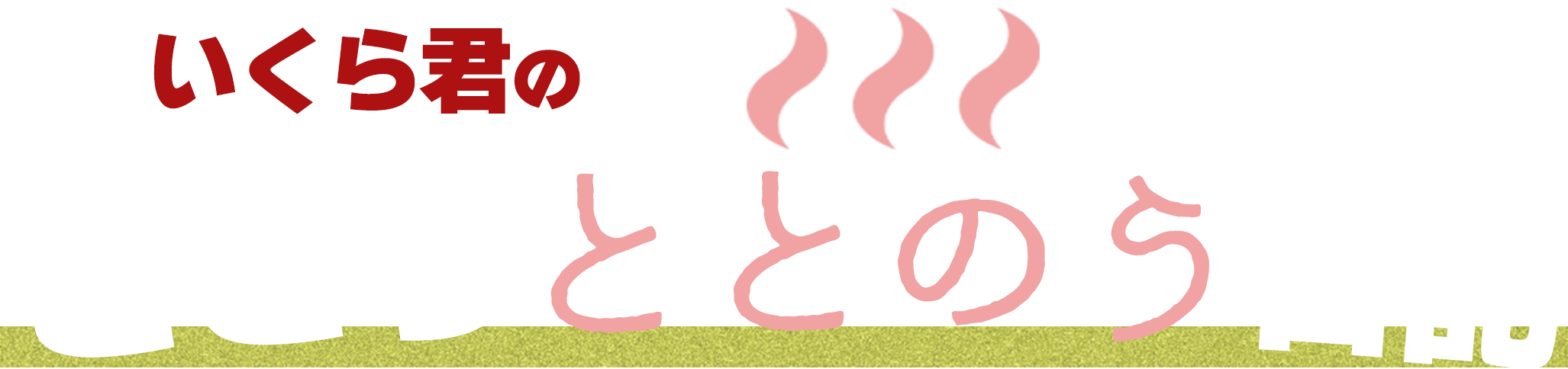ギュスターヴ・フローベール『ボヴァリー夫人』読了
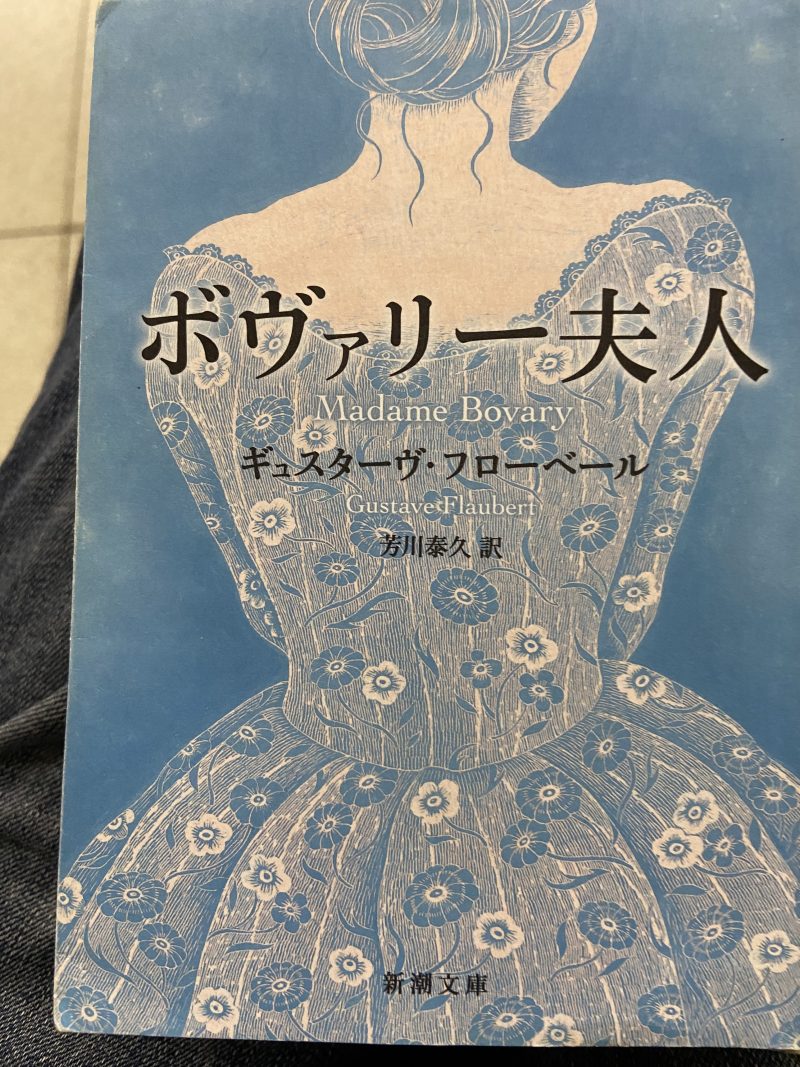
ようやく読了。11月3日から頁をくり始めたのでほぼ一ヶ月かかりました。それは、前半部分の読みになかなか乗らなかったからです。とにかく描写が徹底的に細かいため、悪く言えばまどろっこしい。よって、読み手自身が物語の中に没入できず、なかなか進まないという状態でした。しかし。後半から、つまり、ボヴァリー夫人が色男ロドルフとの姦通し面倒になったロドルフに捨てられる箇所、さらに青年書記レオンとの情事にのめり込む様子や、多額の借金を抱え服毒自殺をするあたりへは、一気に物語に巻き込まれていきました。
ギュスターヴ・フローベールは1821年フランス生まれ。父親は市立病院の医者。兄は父の後を次、フローベル自身は法学生となります。この医学と法学の知識が、小説内ではふんだんに使われています。1851年(30歳)から「ボヴァリー夫人」の執筆が開始され、4年半をかけてこの小説は完成します。「パリ評論」に連載されるのですが、当局からの圧力により、多くの部分を削除し発表したにも関わらず、「公衆の道徳および宗教に対する侮辱」の罪を問われます。いわゆる「ボヴァリー裁判」です。結果から言うと、フローベルー側は勝訴し、そのことが結果的にいい宣伝ともなり、発売後大いに読まれたそうです。
本作の特徴はなんと言っても描写の執拗さです。ストーリー自体は主人公が姦通し借金に塗れ自殺するという、まあ、ありがちなものですが、それを一介の風俗小説ではなく、世界文学にまで押し上げたのは、その描写の力、及び文体の練り込み具合というか工夫であると言えます。フローベールは本作完成までに4年半かけたそうですが、とにかく徹底的な推敲をしたようです。安岡章太郎が、小説は鉛筆ではなく消しゴムで書くものだ、みたいなことをどこかで言っていましたが、まさに書いては消し書いては消し、推敲推敲! その徹底性によって本作は完成しました。とてつもない粘り腰です。また、経済的な後ろ盾があったからこその時間であったのでもあるでしょう。
また、訳者芳川泰久さんが後書に書いていますが、フローヴェルが編み出した「自由間接話法」の駆使が本書の文体を生き生きとさせているということです。いわゆる「神の視点」で描いてしまうと、どこか作り物めいた鼻白むような点が生まれてしまう。安っぽい御伽話になってしまう。語り手が全ての登場人物の内面描写をし、行動を把握している、という立場でいるのは、おそらく近代文学としてはいけていないのでしょう。しかし3人称小説でありながら、フローベールはそこをとても慎重に取り扱い、神の視点を排除する工夫をした。それが、自由間接話法だというのです。なるほど、言われてみれば、翻訳者の苦労と工夫が随所に溢れています。
なかなか読み応えのある作品でした。