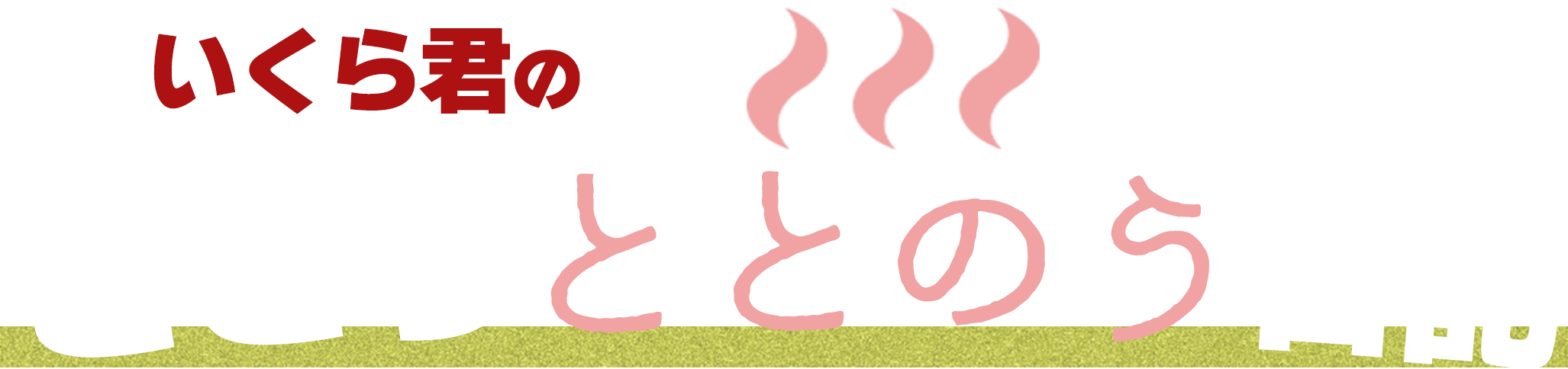ジャン=ポール・サルトル『嘔吐』読了
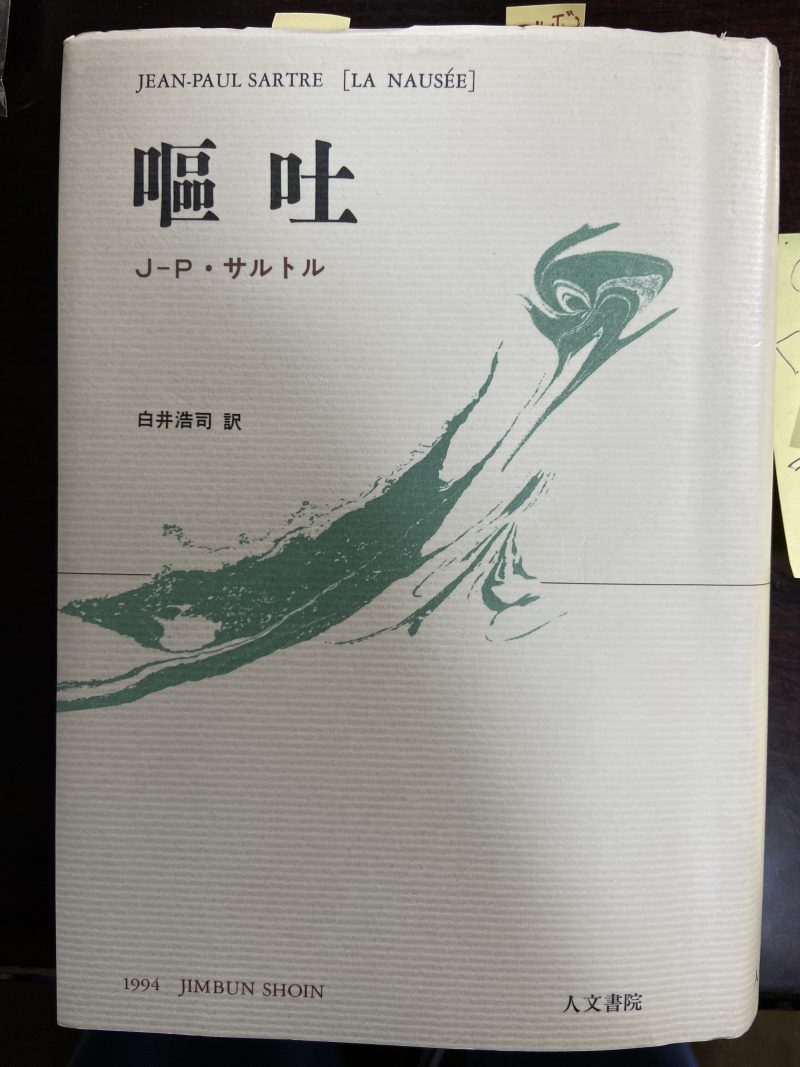
前回のカミュ『異邦人』に引き続き、不条理シリーズ。今回は、サルトル『嘔吐』です。本作は、読み続けるのが、難しく(彼の文章が私を拒んでいる感じ)、なかなか進まず、苦労しました。
サルトルは言わずと知れた「実存主義哲学」の人であります。右目が斜視で特徴的な容貌を持つ方だと、子供の頃から印象深い人でした。肩書きとしては、哲学者というのが
一番に来ると思いますが、彼が世に出た最初はこの『嘔吐』という小説でした。1905年生まれの彼が33歳の時、この作品を世に問いました。1938年のことです。カフカの影響をかなり受けているようです。
さて本作ですが、高等遊民的な生活を送る「アントワーヌ・ロカンタン」が、「ド・ロルボン侯爵」の歴史書を書くため3年前より「ブーヴァル」に滞在しています。本作は、そのロカンタンの日記、という体です。ロカンタンは基本的に図書館で調べ物をし、「鉄道員さんたちの店」で食事をしたり酒を飲んだりしています。そこのマダムとは肉体関係を持っています。
ある日、「水切り」をしようと石を持った際、不思議な不快感に襲われます。彼はそれを〈吐き気〉と表現します。
以後、様々な場面で「嘔吐感」に」襲われ、図書館で知り合った独学者とのランチ中にも嘔吐感に襲われますが、その後立ち寄った公園でマロニエの木を見た瞬間に原因が判明します。
それは「存在」についての気づきでした。全てのものはただ偶然存在し、また自分自身も偶然存在し、その存在に何の意味もない、という気づきが彼に嘔吐感を起こさせたのでした。しかし、「鉄道員さんたちの店」である音楽を聴いている時はその発作が来ないのです。
彼は自己の「存在」について思考を深めるとともに「ロルボン侯爵」の伝記執筆を放棄し、元恋人アニーとの再会と別れを経験し、この地を離れ「パリ」に移住することを決意します。最後に寄った「鉄道員さんたちの店」で、給仕のマドレーヌの勧めで音楽を聴きながら、小説を執筆することが自分を救うことだと決意するシーンで終わります。
全体、辛く苦しい文章に覆われていますが、何らかの結論めいたものを獲得したロカンタンが小説を書く決意をする箇所は、前向きで明るく素晴らしい描写でした。
一般的にわれわれは社会の中である何らかの意味を持って存在していると考えています。しかし、サルトルによれば、われわれの存在に意味など全くないのです。それは演技であり、実存は無であるという結論を得た際の衝撃を理解する必要性を言いたいのだ、と、本作から受け取りました。生きる。食う、寝る。その原点から全てが始まるのであって、虚飾の意味づけを罵倒するサルトルの厳しい捻くれ度が十分に伝わってくる作品でした。