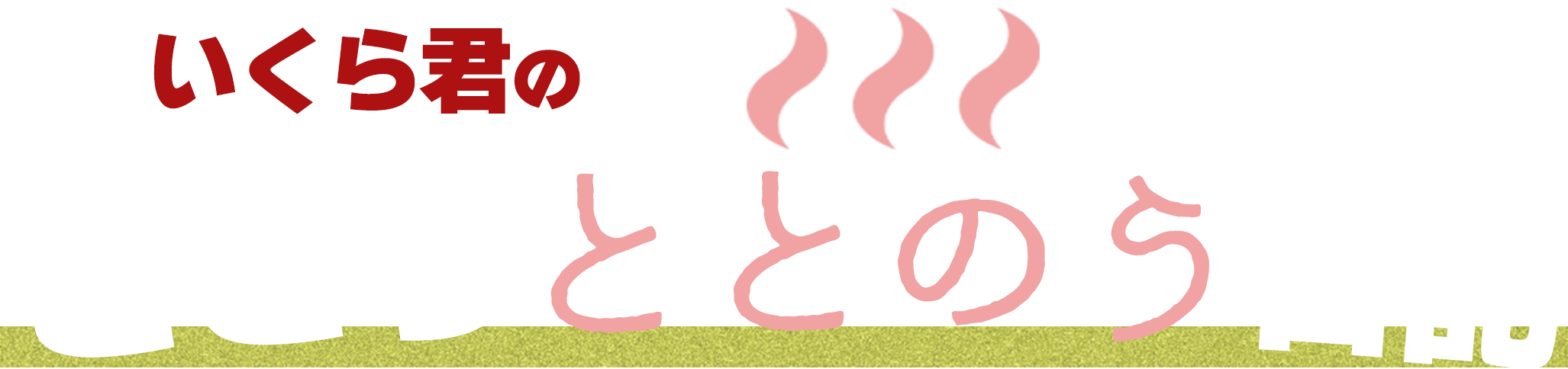水谷千秋『教養の人類史』読了
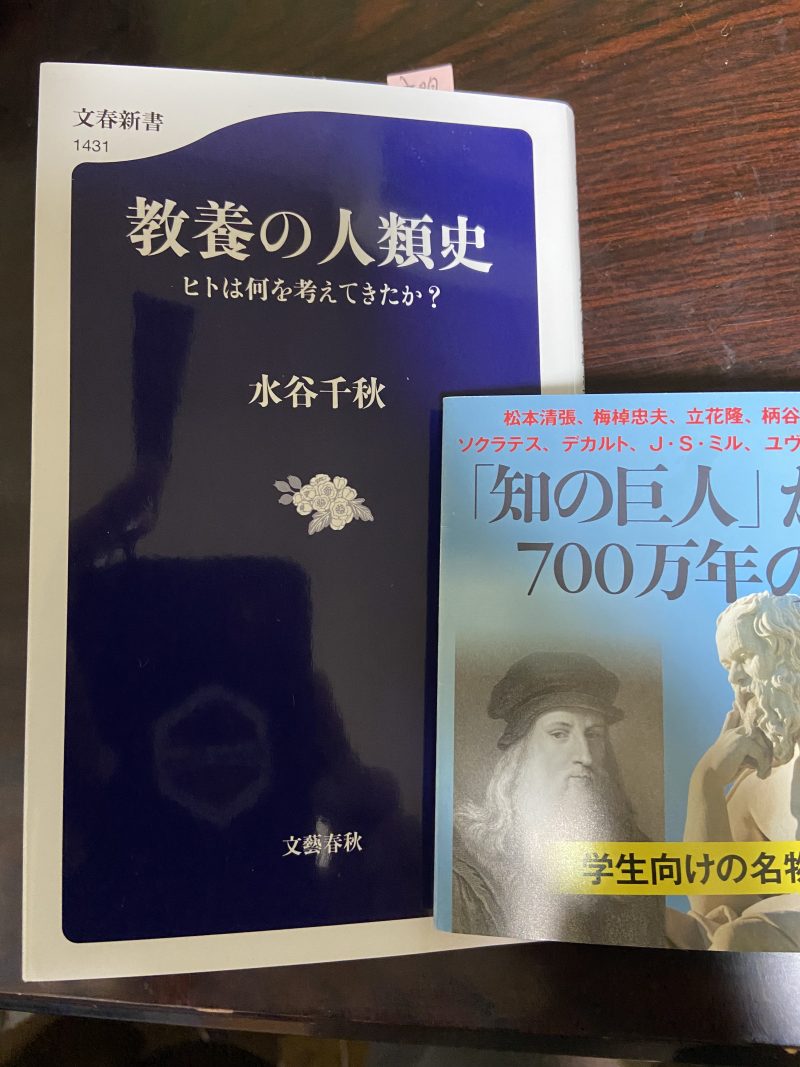
現在、芥研で、柄谷行人『力と交換様式』の読解を進めている。柄谷は、マルクスが「生産様式」を柱に組み立てた理論『資本論』一巻に対し、「交換様式」(物々交換・お金と商品の交換、等々)という概念を柱に、世界の賢者たちの、つまり「巨人の肩に乗り」ながらも自らの考えを理論化・体系化している。それが『世界史の構造』であり『力と交換様式』という形で結実した。その知的で示唆的でありつつも、難解な作品を少しづつ読み解こうとしているのだが、何か参考になるのではないかと、前回はハラリ『サピエンス全史』を読み、その流れで本作を手に取った次第である。
本作で、著者も語っているが、今を生きる我々は恐らくさまざまな意味において、地球のあるいは人類の危機として、現代を捉えていると思う。そこで、知の巨人たちは「知の総合化」「知の全体像の構築」を模索し表現したいという欲望に取り憑かれているように思う。
柄谷にせよ、ハラリにせよ、ジャレド・ダイアモンド(『銃・病原菌・鉄』)にせよ、そういった欲望(使命?)を形にしたいと考えているようだ。本作の著者も同様である。
しかし本作は『教養の人類史』であり、帯には「学生向けの名物講義を新書化!)とある。著者は「いくら君」のに学年下の短大の先生である(さらに専門は日本古代史とある)。よって、どの本でもある程度パターンは同じなのだが、人類の進化・認知革命・哲学・宗教・西欧の世界制覇・産業革命から現代、について書かれることが多い。「いくら君」は最初に、柄谷行人の著作を読んでいるので、他のものがどうも精密さに欠ける印象を持ってしまう。そんなわけで、まあ、気楽位に(少し馬鹿にしながら(水谷さんごめんなさい)、頁を繰り始めたのである。当然筆者の専門外である項目に対しては、引用、引用、まとめ、といった感じで、過去の巨人の思想から一歩も外に出ることなく、粗雑に人類史をなぞっていくのである。ああ、短大生相手の講義が元なので、まあこんなものか、という思いであった(この文言には短大に対する差別的な意識が垣間見え嫌である)。途中、中世日本史の項では俄然筆者の筆は冴えるのであるが、本作のタイトルからは逸脱気味で、鼻白まないわけでもなかった。
第7章「現代史との対話ーー明治維新と戦後日本」は明治維新から配線までが75年。さらに昭和20年からコロナ危機(2022)までが75年と指摘し、それぞれの75年を半分にあるいは4分の1にわけ分析する視点は、これもどこからか借りてきたものかもしれないが切り口鋭く面白かった。
第6章までは「巨人の肩に乗って」いるだけであったが、7章以降は筆者独自の見解が丁寧にしかも自由に語られ興味深い。新自由主義導入以降(レーガン、サッチャー、村山富市)の世界は貧富の差が歴然とし分断が広がってをり、世界は不安定な状態に置かれている。大多数の国の民は不満で爆発しそうであろう(いや、実際に爆発している国もたくさん存在する)。労働価値に数字で換算する社会、あるいは人間の尊厳を踏みにじる世界。その中で、柄谷のいうDのような世界を、斉藤幸平は「コモンズ」の概念で説明する。つまり「コモン」(水や電力。住居、医療、教育といったものを公共財として、自分たちで民主的・水平的に共同管理に参加す」し「最終的にはコモンの療育を広げていく」ことを語ると筆者は紹介する。未来は構築するのは我々自身であり、他者(国、役人?)に任せてのではなく、我々が参加することで良き未来が到来することを示唆する。そして、それを可能にするのは「教養」である、と、筆者は教育者らしくまとめるのである。
本文章にも書いたが、歳者は少し軽く見ていたが、後半は学者というより教育者の実体験から生まれた危機感とそれに基づく漲る気合に圧倒された。「ペスト」の要約では涙しそうに感動した。本作は、彼が小さな専門の井戸に閉じこもることなく、自由に教育者として現代の若者に伝えたいことを書いた、という意味において「短大」の教師でなければできなかった仕事かもしれないと思い直した。
よかった。ありがとうございました。