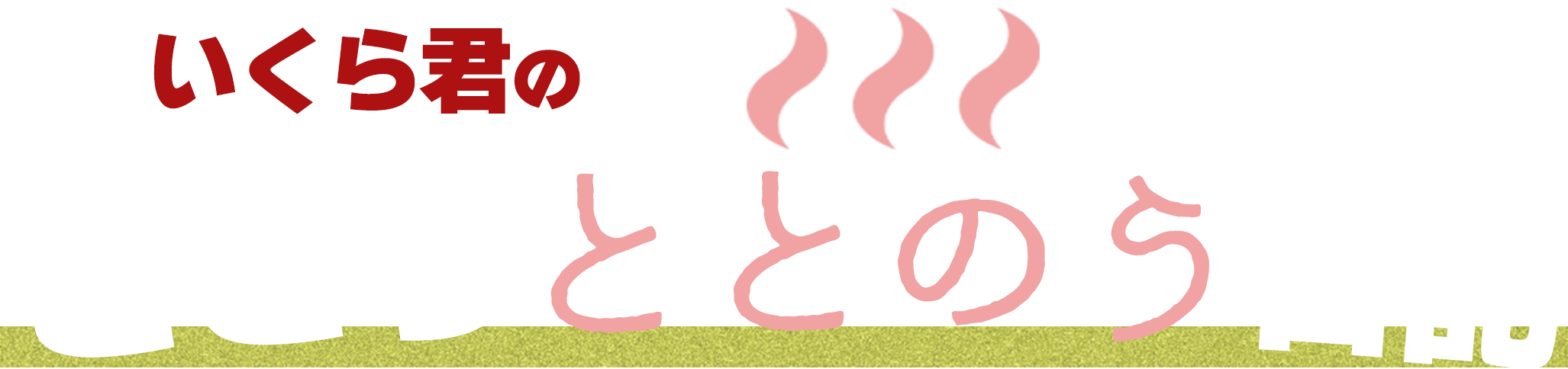竹田青嗣『カント「純粋理性批判」』読了
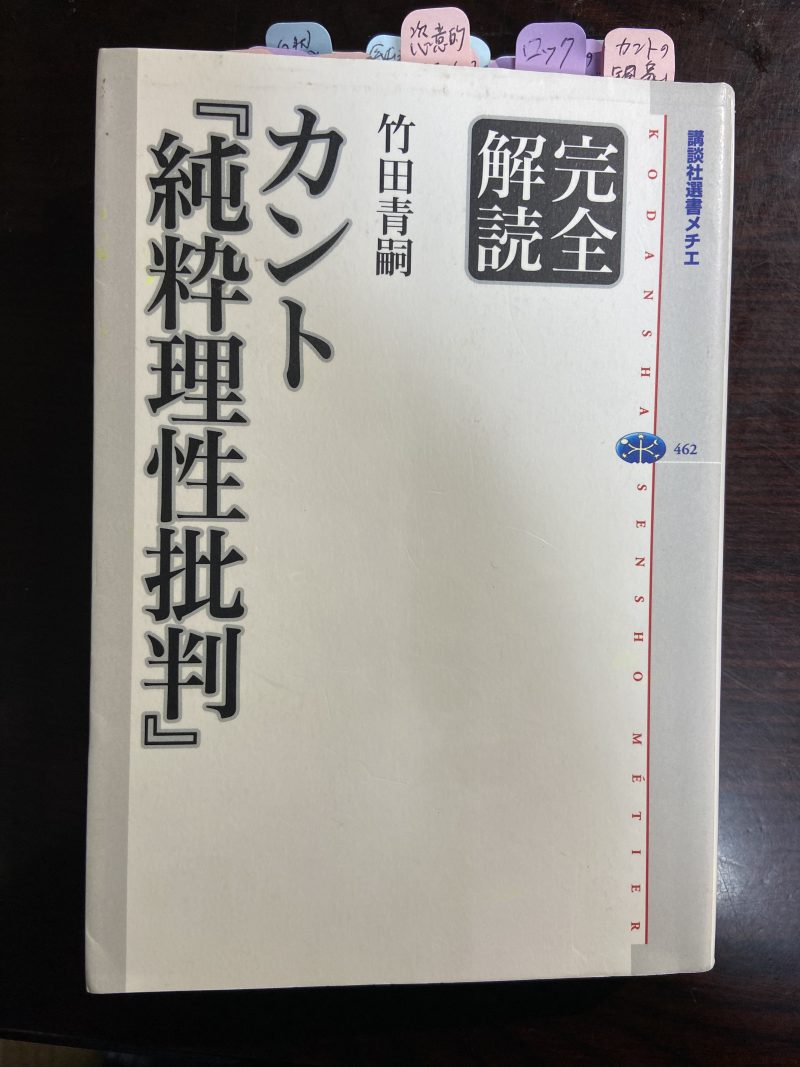
5月9日に読み始めた、竹田青嗣『カント「純粋理性批判」』をようやく昨日(6/2)読了した。いやあ、大変だった。饒舌でレトリカルなカントの文章を、竹田青嗣は簡潔に精一杯わかりやすくまとめてくれているのだが、それでも「いくら君」においては、途中頭がぼうっとし論理が追えなくなり船を漕ぐ始末である。が、どうにかこうにか最終頁に辿り着いた。とても「わかった」などと胸を張れるような状態ではない。部分的には途中でカントの森に迷ったままである。
西研のカントは、西研の言葉で丁寧にわかりやすく置き換えられていた。しかし、竹田青嗣のこの試みは、あえてそれをせず、我々読者に原形に寄り添うよう命じる。
さて、私が本書より学んだことは以下とおり。
カントは丁寧に過去の形而上学の誤謬を指摘し、誰しもが曖昧のままであった事柄に対し交通整理を行うとともに、新たな概念を取り出し?生み出し?(まるで空気中から酸素だけを抽出し、そして見える化するかの如く)名前をつけ整理する。漂うまま区分けされていない漸次的アナログ的哲学言語の世界を、言葉の力のみで事実を切り取り名前をつけ整理する。まるで昆虫採集をし、防腐剤を打って標本化するかのように。そして整理されたさまざまな概念から導き出された最も中心的なカント哲学の要諦を一言で言ってしまうと「わからないことはわからない」(形而上学の不可能性)ということであろう。(この平易な表現には多くの問題があるのを承知であえて言う)
ギリシャ哲学より、千数百年にわたり人類の叡智は「神の存在証明」に対し二派に分かれ議論を重ねてきた。つまり「神は存在する」VS「神は存在しない」という具合に。しかしカントは人類の哲学史に大きな杭を打ち込み流れの方向を変えた。それとともに今後の人類の方向性を決定づけたと言っても過言ではないだろう。
カントはアンチノミー(二律背反)の思考法でさまざまな議論を整理し、客観的事実のように振る舞ってきた過去の言葉を独断論として退け、我々には「真理」の姿を現前させることはできないのである、ということを明確化する。
「こうして、双方の主張、つまり世界についての独断論と懐疑論の双方の主張が、じつはともに、原理的に確証できないものを絶対的に正しいと主張する「独断論」であることが明らかになる」(竹田p284)
「世界は「一」であり、「無限」であり、「神」であるというスピノザ的独断論に対する、ヒュームの経験論的懐疑論、われわれの世界の全体について完全な認識を持つことは決してあり得ないという議論は、大きな意義を持っていたし、また理論的(筆者棒点)にも大変正しかった。にもかかわらず、ヒュームの議論は、いま示したような双方の独断論の必然性と動機(=関心)の深い理解にまでは達していない。(竹田p286)
カントにおけるアンチノミーの要諦は「形而上学の不可能性」の原理ということだ。その上で、我々は何をどうのように考えていくべきか。という航路を開いてくれたのがカントの最も大きな成果なのであろう。
⭐︎『純粋理性批判』全体構成
Ⅰ 先験的現理論→第一部門 先験的感性論 時間・空間
第二部門 先験的論理学
第一部 先験的分離論 概念の分析論
カテゴリー 原則の分析論 判断力
第二部 先験的弁証論 純粋理性の誤謬推理(魂)
先験的宇宙理論 アンチノミー(世界)
純粋理性の理想(神)
Ⅱ 先験的方法論→第一章 純粋理性の訓練
第二章 純粋理性の規準
第三章 純粋理性の建築術
第四章 純粋理性の歴史
さて、このまま『純粋理性批判』(岩波文庫 篠田英雄訳)に直進すべきなのであろうが、流石にちょっと疲れたので寄り道することにする。それにしても、西欧における2千年の思惟の歴史の重厚さは大変なものである。カントーヘーゲルーフッサールーハイデガーとのドイツ語での思惟の流れ、そしてフランスにおける現代思想の流れ、それらの重厚で多様かつ饒舌な思惟の歴史は、何事かを常に明らかにしようとする、我々サピエンスの強い欲望の一つの現れ方である。東洋のそれは、真に近づきたいという欲望を動機とする点において同じだとしても、アプローチ方法が方向が全く異なる。西洋哲学のように知を言語で語り尽くそう、という意思にも魅力はあるが、東洋的な到達の仕方にも当然興味がある。私はいつか、禅的世界の研究に向かうような気がする。
さて、次は何を読もうか? 「気絶するほど悩ましい」(チャー或いは阿久悠)