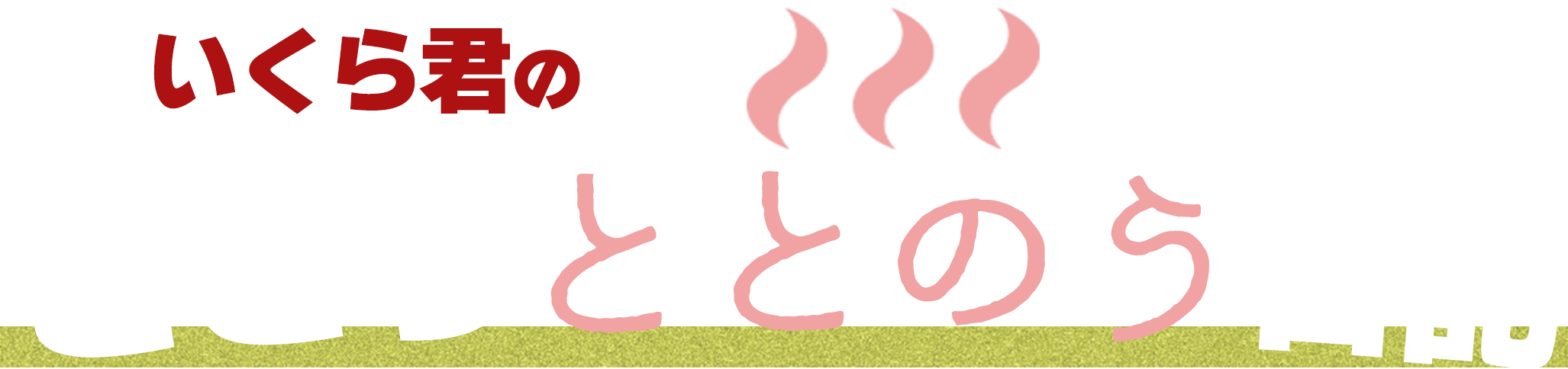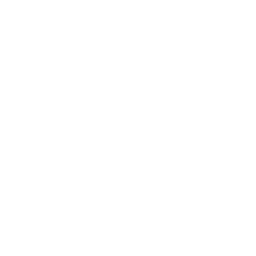浜松祭り





5月4~5日,一泊で浜松に行ってきました。完全形での祭りは5年ぶり。昨年の今頃はまだ5類に移行していなかったのですね。
目的は浜松祭りなのですが,きっかけは娘の相方が多感な思春期を過ごした場所,つまり転勤族であるあちらのご両親が子どもらと比較的落ち着いた生活を送っていた場所だからです。
あちらの親父さん(エネルギッシュで大変愉快な方)は大の祭り好き。5年前案内してくださり,我々夫婦も大の浜松ファンになったという次第です。
祭りは二段階に別れます。前半は砂丘にて凧揚げ。夕方からは中心部で屋台の練り。ラッパ隊が独特な音楽を響かせ,祭りに活気を与えます。
地元の方々は皆法被を羽織,精一杯のオシャレをして屋台を引いたり,提灯を掲げ練りを盛り上げていました。
しかし,気のせいかもしれないけれど,以前よりおとなしいというか,破壊的な力が幻滅し,上品になってきているような気がします。
これも世の流れなのですかね? 権力からの規制あるいは忖度による自主規制? 継続するには避けられないとはいえ,やはり寂しい。
今の若者の中には,「盗んだバイクで走り出し🎵」と尾崎の魂の叫びを聴き,悪いことをしてけしからん!と本当に思う奴がいるとか。
こうなると嘆かわしいの一言になってしまいます。
孫の青春時代のデフォルトはどうなっているのかなぁ。
話がそれました。娘夫婦にも向こうの両親殿にも大変お世話になった二日間でした。
ありがとうございました。またよろしく!
夏野菜ひと段落







トマト・きゅうり・ナス・ピーマン等の夏野菜の苗定植を終え、とりあえずひと段落です。
私がお借りしている農地は飛び地だったのですが,お隣が撤退したため,1aほどの土地4面を連続的に使えるようになりました。さらに冬でも使える(日が当たる)土地が増えました。
そこで昨年の12月後半から1月下旬にかけて,3面の土作りに精を出してきました。まずカチカチになった土をスコップで30cmほどの深さで起こします。その際・蠣殻石灰・米糠・鶏糞・カルスNC-rかAG土力(土壌改良資材)を混ぜ込みました。完全に人力のみで20日かかりました。
2月すぎからは年越し野菜(玉葱・大蒜・ラッキョウ・絹さや・スナップ・グリーンピース)のお世話が始まり、同時に春先に食べられるようにと,ビニールトンネル内に小松菜・ほうれん草・ミニ大根・カブ等を播種しお世話をしました。
3月にはその年の実質上の畑始めと捉えている馬鈴薯が始まります。今年は実験で購入した種芋以外に昨年採取したの物も植えてみました。正確な結果はまだ出ませんが,やはり買った種芋の方が成長がいいようです。しかし,冬場の管理の問題でもあるので,さらに研究し,種芋を買わない,永遠サイクルを目指します。
4月は里芋。これも種芋を購入しましたが,冬場の管理を工夫したいと思います。中旬は生姜定植。
また2月から自宅で播種し育ててきた苗たち(レタス・ブロッコリー・南瓜・キャベツ等)の定植。
その間,葉物をちょこちょこやり,そしてようやく夏野菜(トマト各種・ナス各種・胡瓜・シシトウ・ピーマン・唐辛子・スイカ)定植とすすみました。
また,枝豆・インゲン・ツルムラサキ・オクラ等を播種しひと段落しました。
当然終わりはありません。お百姓さんというだけあり仕事は無限にあります。日照りにヒヤヒヤし,長雨に心痛め,草むしり草刈り,土作り,播種・追肥・・・。キリがありません。
が,とりあえずここでひと段落しました。
あとは基本的にはお日様にお任せしましょう。私は少しお世話をするだけ。あとは自然の恵を静かに待ちます。
あ,今月下旬にはサツマイモの定植があります。そこの土作りをせねば。
百姓には基本休みはありませんな。疲れますが,喜びです。
さあ,今年は昨年以上に美味しい野菜をたくさん作ろう!
千葉雅也『勉強の哲学』読了
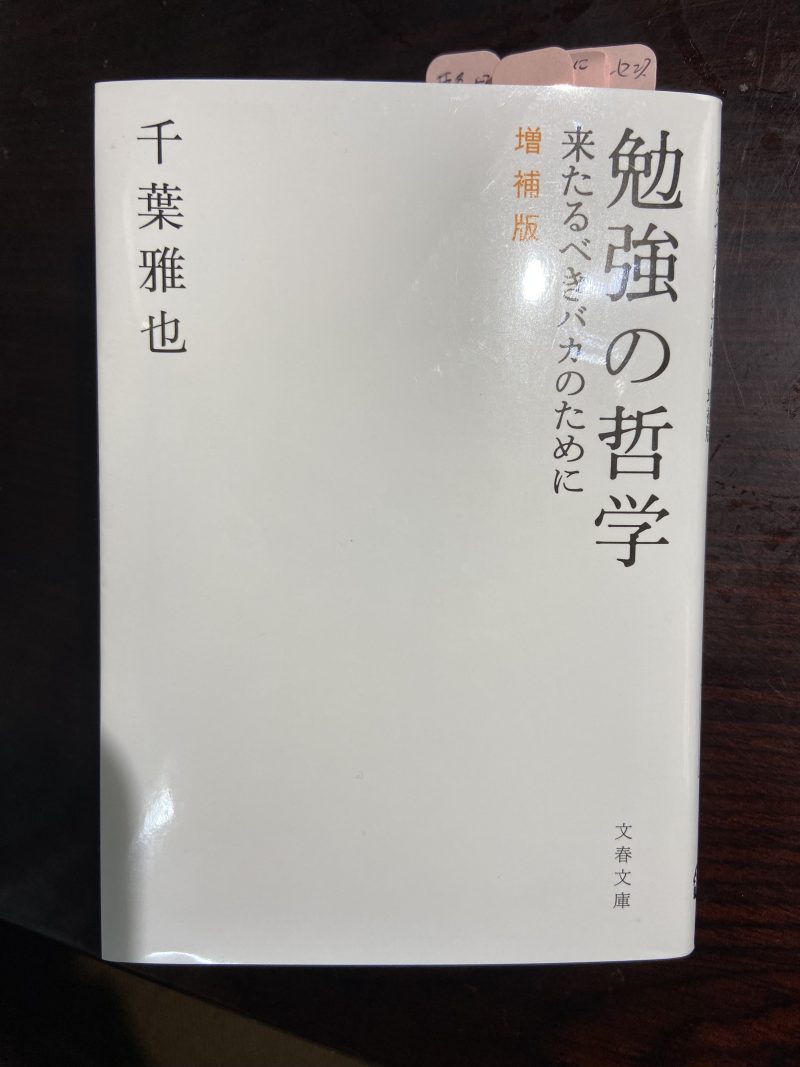
筆者「千葉雅也」は、フランス現代思想の研究者であり、立命館大学教授であり、小説家でもある。ドクター論文のテーマが「ドゥルーズ=ガタリ」だというから、フランス哲学あるいは言語論(ビトゲンシュタイン)を掘り下げてきた人のようだ。1978年生まれであるから現在45歳。本書上梓が2017年4月であるから30代後半の作品ということになる。
本書は4章に分かれ展開する。
1章「勉強と言語」我々は通常社会のコードに支配され日常を過ごしている。勉強とはそのコードを破壊することである、と筆者は述べる。「勉強とは、自己破壊である」と。「ラディカル・ラーニングとは、ある環境に癒着していたこれまでの自分を玩具的な言語使用の意識化によって自己破壊し、可能性の空間へ身を開くことである。」
さらに2章では自由になるための思考スキルとして、「アイロニー」と「ユーモア」を紹介する。「根拠を疑って、真理を目指すのがアイロニーである。根拠を疑うことはせず、見方を多様化するのがユーモアである」。さらにこう付け加える。「勉強の基本はアイロニカルな姿勢であり、環境のコードをメタに客観視することである」が「アイロニーを過剰化せず」「ユーモアへ折り返す」ことを筆者は薦める。アイロニー過剰は絶対真を得たいという、実現不可能な欲望に支配されることに繋がるからだ。つまり、「言語はそもそも環境依存的でしかないということを認め」なければならない、絶対真に向かうのもいかんのである。
3章「どのように勉強を開始するか」?そのためには「まず自分をメタに観察し」「現状に対する別の可能性を考える」必要がある。つまり「環境のなかでノっている保守的な「バカ」の段階から、「メタに環境をとらえ、環境から浮くような小賢しい存在になることを経由して、メタな意識を持ちつつ」「享楽的こだわりに後押しされてダンス的に新たな行為を始める「来るべきバカ」になる」のだ。
第4章「勉強とは、何かの専門分野に参加することである」。まずは入門書を複数通読し全体像を掴む、そこから深入りしていくのだ。しかし、筆者は優しい。というのも「完璧な通読」はできないという意識で取り組め」といってくれるからだ。さらに読書の基本的方法は「これまでの自分の実感に引きつけて読もうとしない」ことである。勉強においてはテクストを文字通り読み、「自分なりの理解」と「どういう文言で書いてあったのかを区別しなければならない」。なぜならこの区別を曖昧にしていると知らぬ間に剽窃してしまうからだ。その防止に「読書ノート」を作るとともに「出典」を伏すことが大切だ。そのための、日々ノートアプリに向かう必要性を訴える。
前半は理念的に、後半は実践的に勉強とは何か? 勉強をすることの意味。さらに勉強の仕方を具体的に提示してくれる。筆者はまだ若いがこれからさらに世界の言論あるいは哲学界さらに小説界をマルチに遊びながら知的リーダーとして成長していく人物であると確信する。
森永卓郎『書いてはいけない』読了
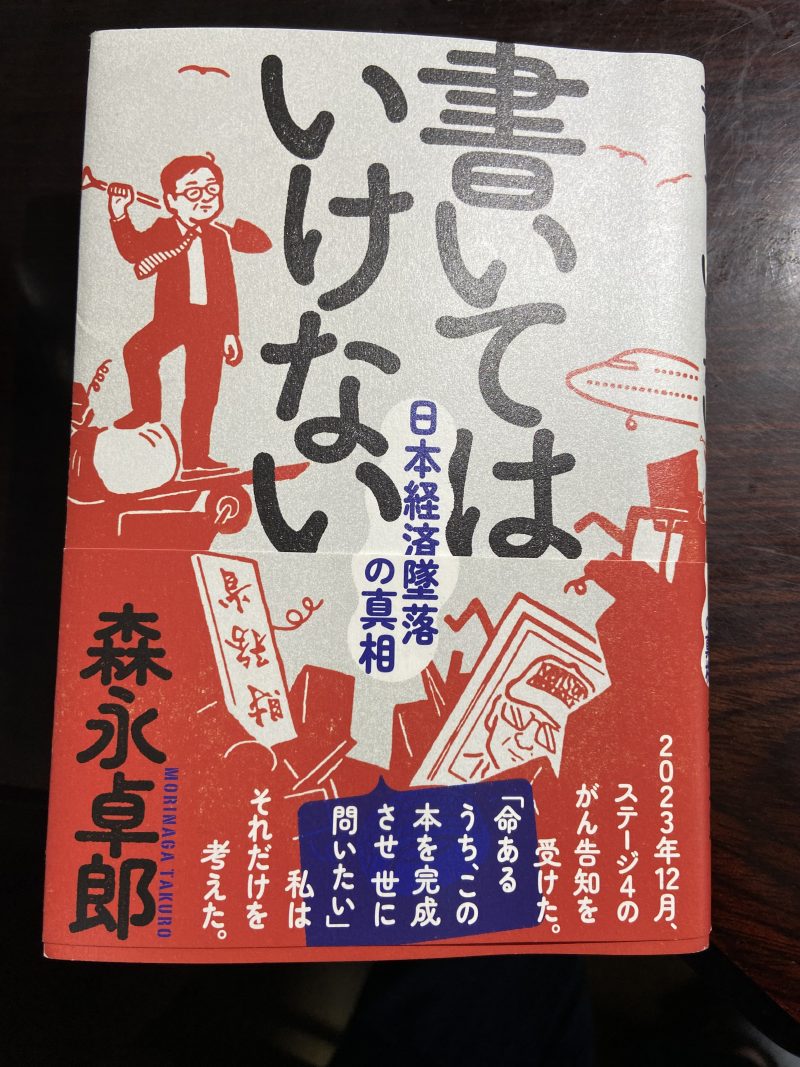
森永卓郎『書いてはいけない』読了。
本作は、2024年1月に上梓された、いわば、筆者畢竟の暴露本である。内容は〈ジャーニーズ問題〉〈財務省問題〉〈日航ジャンボ機問題〉の3点である。いずれの問題にも共通することは、巨大な力を持った(利権に塗れた)組織が、自らの不正を隠蔽すべく、マスコミを配下に納め庶民に不利なプロパガンダを行なっている。それは著者森永氏は命をかけて告発するというものである。
それぞれ大変大きな問題を抱えており、また現代的で示唆が多かった。財務省の権力構造はそこまで行っているのか!政治家もマスコミも言論人も司法も彼らの意のままであるという。
また日航ジャンボ機事件の裏側にはそんなことがあったのか!という素朴な発見と、それ以降の日本のアメリカへのポチ化の理由がよくわかる。多分、森永氏はいい人なのであろう。また、いつまでも子供の心を忘れず長い物に巻かれない清い心を持った人なのだろう、そいう想像がつく。昔から彼をテレビで見ているが、どうやら正しいことを言っているようであるが、どうも周りにあまり相手にされない、あるいは取り上げられることも少ない。しかし、消えることもない。これは一体なんだろう? 本書はおそらく真実が書かれているのだろう。また、言論の場で彼は真実を語っているのであろう。しかし、どうにも、そこには迫力というか毅然としたものというか、そういった力が見受けられない。どこか飄々としている。それが彼の魅力であろうが、また彼の弱点でもあると思う。ちなみに作者は昨年(2023)12月余命4ヶ月の癌診断を受けたという。時間はもうそこまで迫っている。しかし、テレビも新聞も彼のこの言論・暴露を相手にしない。悲しいことである。
柄谷行人『トランスクリティーク カントとマルクス』読了
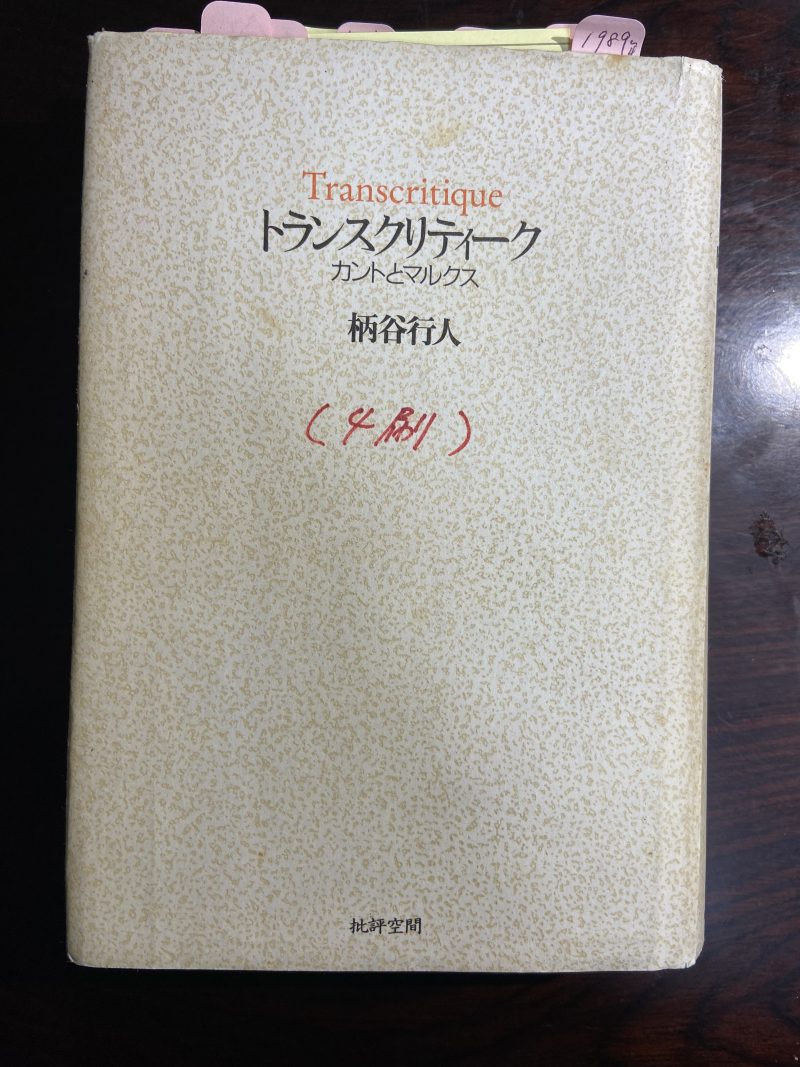
柄谷行人は2022年10月に彼の思想の到達点ともいえる『力と交換様式』を発表した。
これは資本主義の核心を追究する野心作であり、それを交換様式から見るという試みである。交換様式を武器に四つの事象を分析してみせる。その手腕はてだれており、彼自身の人生を大半をこの思考に回してきたため、練りに練られ、考えに考えられてきた思想であるため、難解ではあるが、非常に丁寧で例もわかりやすく、親切に我々読者を彼の思想に導く作品であった。
ちなみに柄谷は1941年生まれである。本作発表時が81歳である。そのほぼ10年前に『世界史の構造』という大著を世に問うている。
あらわれたものは違うが、根本にあるものは両者とも「交換様式」を軸に考察していく手法である。この2作の原点となるものが、今回の『トランスクリティーク カントとマルクス』である。柄谷はカントからマルクスを読み、マルクスからカントを読むといった交差した思想から新しいものを生み出す手法を「トランスクリティーク」と名付け実践してきた。ここでは柄谷自身がカントとマルクスを引用しながら考察を深めていくのであるが、彼自身まだ何が出てくるのかわからないような状態で、模索し思考しながら叙述しているといった感じであるため、思考の流れが整理されておらず、読者にはわかりづらい。
『世界史の構造』『力と交換様式』は非常に整理されており、読者に対し親切であるが、『トランスクリティーク』は荒削りである。筆者もまだまだ若いということであろうか。誰が親切に欠いてなどやるものか、といった尖った矜持がある。(若い!彼はこの時、還暦であった!)
そして柄谷は、本作末びでカントとマルクスを批判しつつ、国家という暴力装置をアウフヘーベンした、アソシエーションを提唱するのである。その発見がのちの作品原点となっているのだ。
西研「カント純粋理性批判」100分で名著
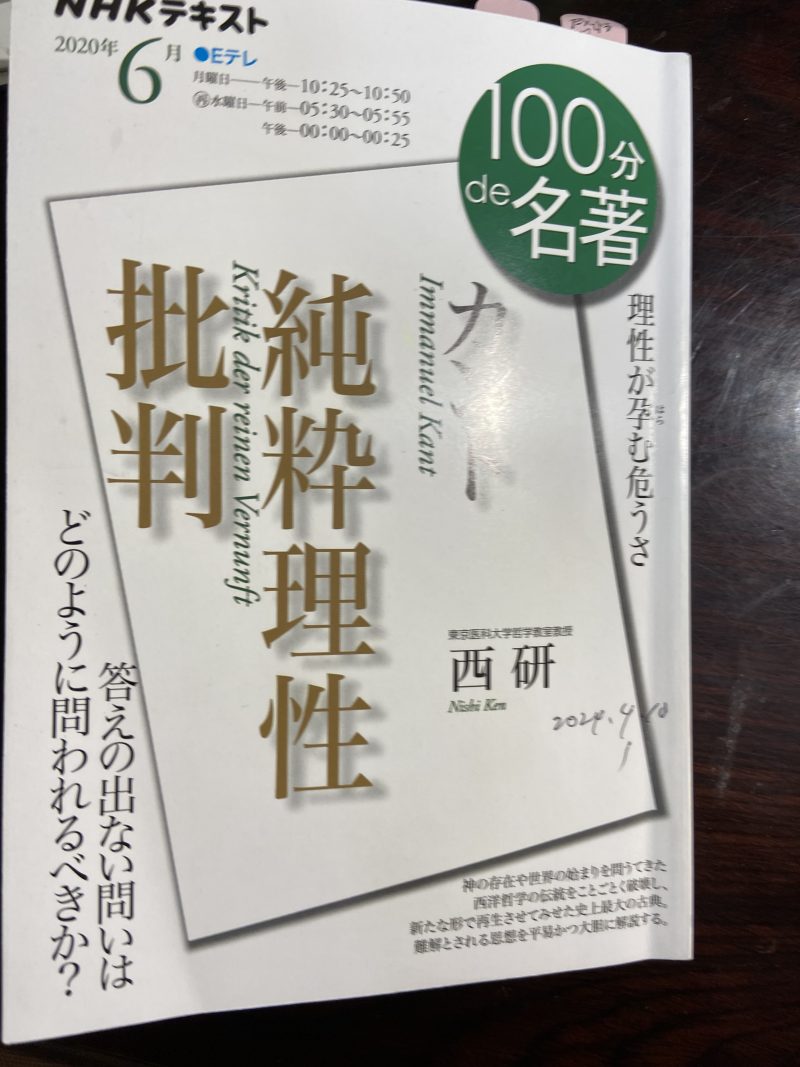
長く、柄谷行人の著書に関わっている。順番としては、あまりよくないのだが、『世界史の構造』『力と交換様式』そして、それらの原点でもある『トランスクリティーク カントとマルクス』と進んでいる(途中、関連文献や関連書に手を出したが)。この本は一部で「カント」を扱い、二部で「マルクス」を取り上げている。数日前、一部つまりカントの項を読了した。難しい内容であった。とてもカントを分かった(そんな日が来るかわからないが)と言える状態ではなかった。用語の難しさがある。それを辞書で引き確認してもどうにもしっくりこない。このまま「マルクス」に行ってもダメだと思い、「カント」『純粋理性批判』の入門書にあたり、ざっくりと全体像を掴むべきだと判断した。まず最初に手にしたものは、竹田青嗣『完全解読カント『純粋理性批判』』である。前書きからパラパラ見ていると、これも相当に難解そうである。もっと超入門書的なものははないか。そこで出会ったのが、難解な哲学を優しいく解説する手腕に優れた西研のNHK100分de名著「カント純粋理性批判」である。
通読した結果、カントがこの本で言おうとしたことの概略が掴めたような気がする。当初「認識」という言葉がやはり掴めずにいた(この言葉は三島由紀夫の所作品、特に『金閣寺』における柏木の認識、また『豊饒の梅』の副主人公たる「本多繁邦」の認識論、そして彼の惨めな終末、などの考察に必須の考え方である)。
どうにか西研の導きで「人間は何をどのように認識しているのか、その時理性はどのように働くのか」という「認識論」の第一歩を理解した。カントの問題意識は人間が認識できる世界(現象界」と認識できない世界(物自体・叡智界)を区別し整理したこと、さらによく生きるための自由や道徳に対する考察などであることをある程度理解した。
今後また、柄谷行人『トランスクリティーク』第二部に戻り、マルクスの箇所を読んだ上で、『資本論』第一部に手をつけたいと思っている。また、そのうち「カントに」戻ってくると思う。
エイプリルフール
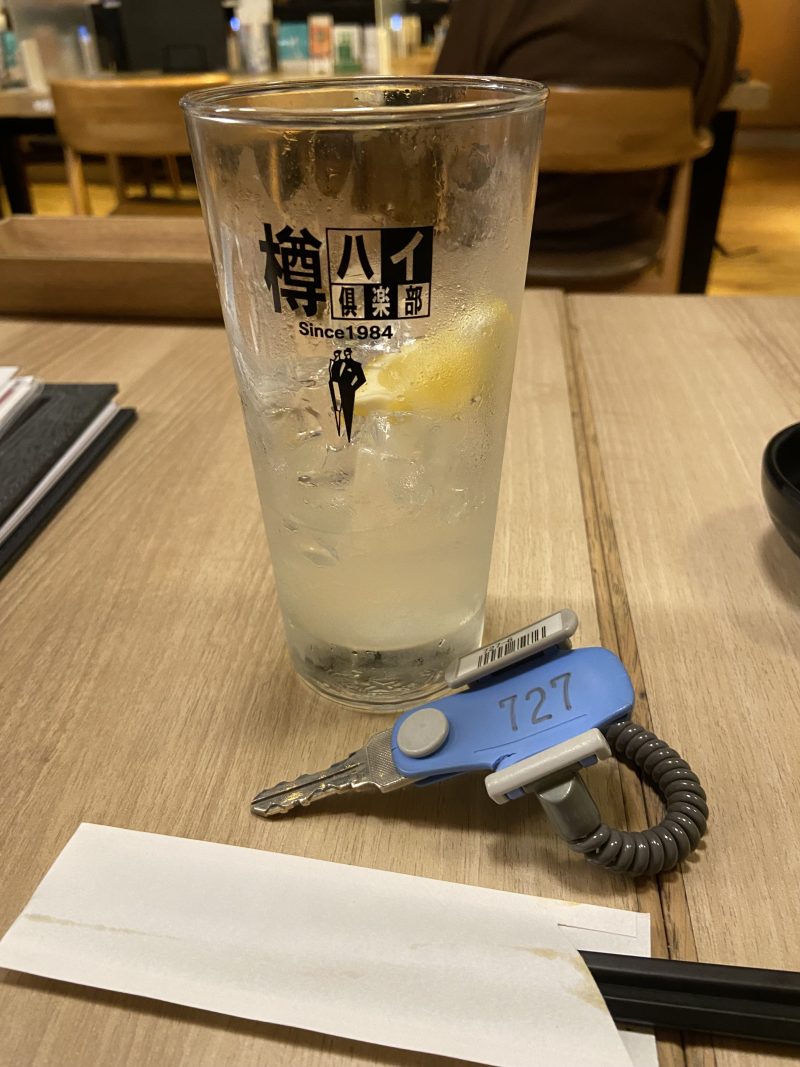 今日は4月1日。年度の始まりである。スカイスパは若者が少なかった。新しい年度で忙しいのだろう。
今日は4月1日。年度の始まりである。スカイスパは若者が少なかった。新しい年度で忙しいのだろう。
今日が4月1日ということは,昨日は3月31日である。さまざまな文芸雑誌が新人賞の作品を募集するが,3月31日〆切というものがいくつかある。
昨年度62歳で仕事を完全に辞め,6月に100枚程度の中編を書いた。7月に芥研のみんなにzoomでご批評いただいた。なかなか好評であった。調子に乗ったいくら君は9月10月2ヶ月かけて,300枚程度の長編を書いた。1ヶ月かけて推敲し,芥研のみんなに読んでもらい,1月14日にズーム会議で批評をいただいた。
散々な評価だった。久しぶりに精神的にダメージを受けた。もうこの世から消えたいと思った。友人とか信頼とかいった言葉も全て崩壊した感じであった。それから2週間ほど辛い時間が続いた。畑で鍬を振ることで少しは紛らわせたが,それでも人間不信というか自己嫌悪というか,とにかく思考が全てネガティブに向かう日々が続いた。
研究会の後数日は推敲に時間をかけたが,すぐバカらしくなった。もう何もかもやめようと思った。こんなものは捨ててしまおうという気持ちと,いやいや手直しして少しでもマトモなものになるまで頑張ろうという二項が自分中で攻めギ合い,結局放置した。この苦しみから逃れようと一時的に逃げた。 3月になった。やる気が起きない。誕生日が過ぎたが,やはり放置したままだった。雨が多く,天候不良で桜の開花も例年になく遅い。
3月28日になった。時間がない。やろう!
久しぶりにWordを立ち上げ全編を読み直し,最初のシーンを簡潔に書き換えた。読んでいてダルいところはバンバン切った。で,完成とした。270枚であった。
「新潮」に応募しようずっと考えていた。とりあえずできたので,応募要項を確認してみた。あらら。250枚までだって! しまった。あと20枚削れないかしらと見直そうとしたが,もう面倒くさい。調べると「すばる」がやはり3月31日〆切であり400枚までOKであることを発見。でも「すばる」はエンターテイメント性が高くなきゃダメだろうと思った(集英社だし)。でももうなんでもいいや!参加することにも意義があるだろう!
ということで,8ヶ月煩悶し続けた文章の群れにお別れをいたしたのでした。
結果はどうせダメなのだろうが,引きずっていたなにものから解放された感じです。
お疲れ様でした。
中島義道『カントの人間学』読了
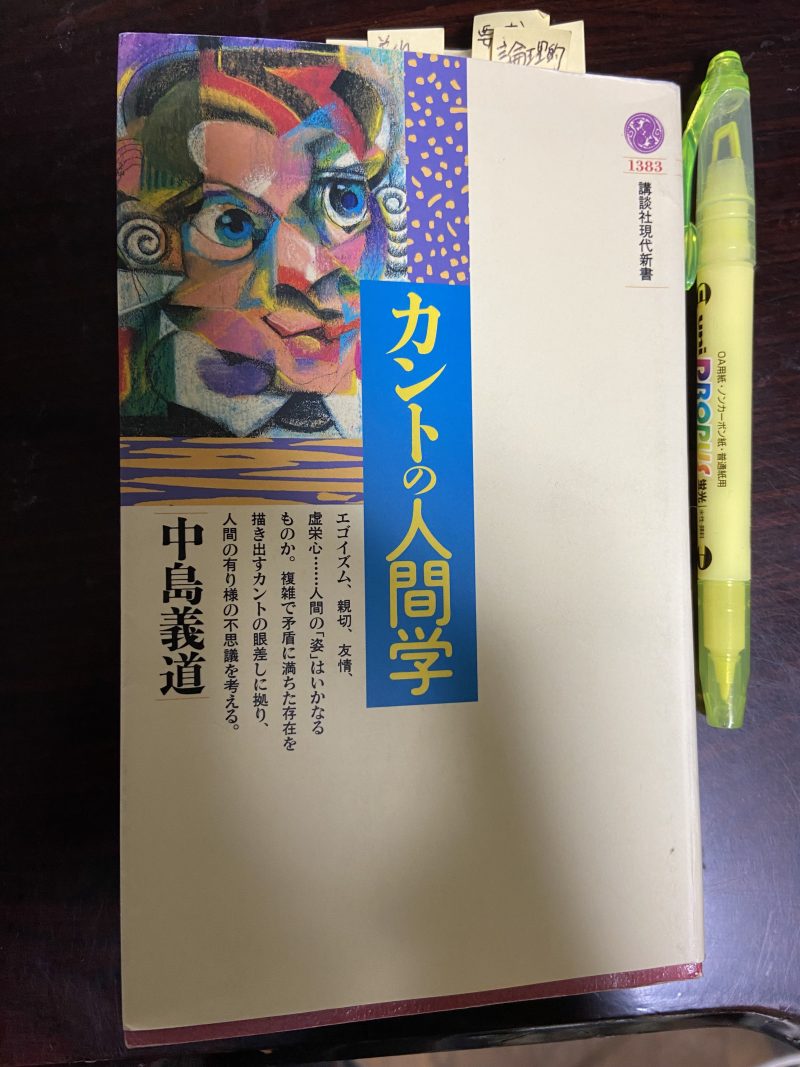
イマニエル・カントと言えば、言わずと知れた18世紀プロイセンの大哲学者で『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』の三大批判書を発表し、認識論におけるコペルニクス的転回をもたらした人物と知られている。しかし、私を含め多くの人間がその著書名を知りながらも、あまりに難解なためなかなか読み通せていないというのが現状ではないか?
著者、中島義道はカント研究者であり、軽妙かつシニカルな文章が魅力の哲学者である。カントに『人間学』という著書がある(ちなみに岩波文庫にかつてあったが現在は絶版で、Amazonでは古書で9700円の値がついていた)。それの解説書かと思って本書を開いた。でも、どうやら違うらしい。カントが考える人間についての書であり、カントという人間の書でもある。
あとがきにある。「本書はカントを「モラリスト」として読み解く試みであるが」モラリストの概念は幅広く難しい。そこで著者の定義は「モラリストは人間の多様性を信じていると同時に、人間が複雑極まりなく、矛盾だらけであるという(歴史・文化・階級を超えた)普遍性を信じている。」とする。モラリストの要件とは「あくまでも関心の中心は「人間」であり、しかも人間集団ではなく個々の人間である。崇高かつ卑猥で、勇気に満ちかつ臆病で、聡明かつ愚劣で、冷酷かつ情愛ある個々人の姿をそのまま映し出すことが関心の中心である」ということになる。
本書は、我々人間が悩み陥り苦悩する問題(エゴイスト・親切・友情・虚栄心)などについて、カントの箴言やカントの周りにいた人間の言葉を引用しながら、問題を追求しつつカントの人となりを浮かび上がらせる。
カントのイメージは、峻厳・厳格・自己抑制的など厳しいものであるが、筆者は「私は意図的に旧来のカント像の破壊を狙った」のである。人間らしく滑稽で名誉欲に満ちた人間カントを親しみある存在として描く、ある種のカント入門書である。
柄谷行人『哲学の起源』読了
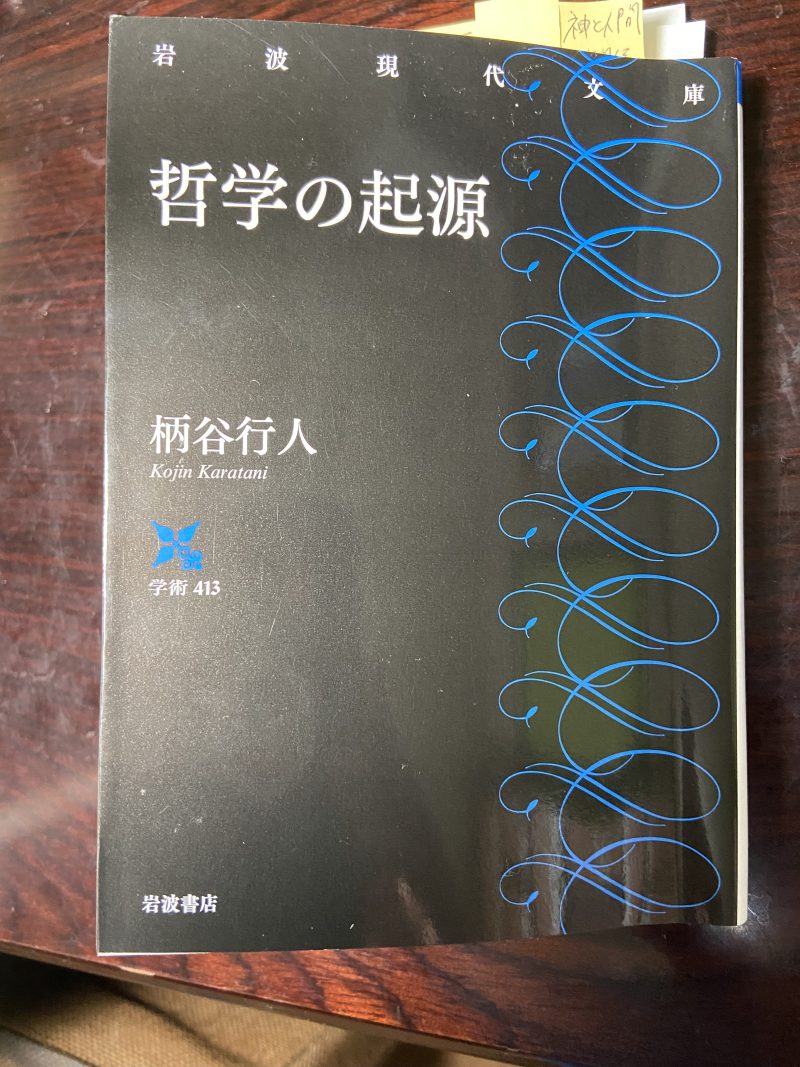
柄谷はいう。「『世界史の構造』は、世界構成体の歴史を「交換様式」から見る企てである。それは社会構成体の歴史を経済的土台から見たマルクスを受け継ぐものである」と。そして、『世界史の構造』でギリシアの時代に向き合った際、さまざまな研究をし思考を深めた。もちろん、彼ならではの新しい発見も豊富にあった。しかし、それを盛り込んでは『世界史の構造』の焦点がぼやけ破綻してしまう可能性がある。そこで断念していた考察を『世界史の構造』発表の2年度(2012)に、『哲学の起源』として新たにギリシャ哲学の発祥を中心に深掘りしたものが本作である。
一般的にアテネはデモクラシーの起源であり、ソクラテスープラトンの系列が哲学の始祖である、といった理解されている。が、柄谷はその一般論に疑義を申し立てる。アテネはデモクラシーであったが、そこには奴隷制度があり、外国人はアテネ市民になれない。市民は政治活動で忙しく、労働を軽蔑している。それは奴隷がやることだ。デモクラシーとは所詮クラシー(支配)なのだ、という具合に。
そのアテネに対立する形で彼が担ぎ出すのが、エーゲ海を挟んでギリシア対岸にイオニアだ(現在はトルコ西部)。イオニアにこそ、哲学の起源があり、また柄谷のいう交換様式Dが存在していた。それをイソノミアという。イオニアは真に自由で平等な国であった。彼らは植民である。つまり、氏族社会的な縛りから自由である。みな自分の土地を持ち労働し身分差もなく自由である。王は存在しない。合議制である。そのDの世界はまもなく、他国に侵略され崩壊するのであるが、イオニアの自然哲学の流れを持った人々がアテネや他のポリスで活躍する。その代表者がソクラテスである。ソクラテスはアテネ市民である。しかし政治に関与しない。それはダイモン(心の声)により、政治に参加してはならぬという命を守り、そして広場で誰かれなく語りかける。彼は何も教えない。ただ対話によって、相手の主張の矛盾をつき、その彼が自ら真実に気づくのを待つ(産婆法)。しかし、ソクラテスは民主派から訴えられ毒杯を仰いで死ぬ。著作は何もない。ソクラテスが目指した世界はイソノミア(無支配)であった。僭主を作らせないことである。しかし、弟子のプラトンが目指すものは哲人王(つまり哲学者が王になるか、王が哲学者になるか。いずれにせよ哲学者が国家を導くシステム)である。師匠と弟子では目指しす方向が丸切り逆である。しかし、プラトンはソクラテスの名をかり自身の哲学を著作として残す。
世間一般に流布する誤解を解こうといういう試みだと考えても良いかも知れぬ。
柄谷行人『「世界史の構造」を読む』読了
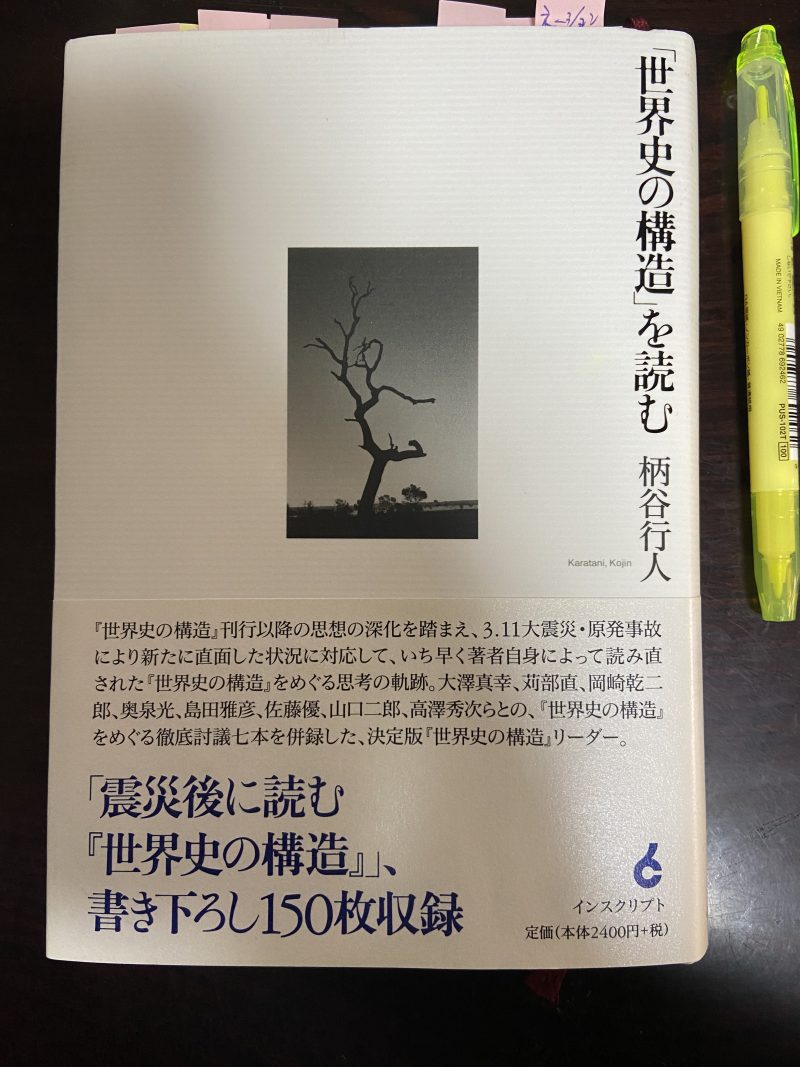
先日、読了した『世界史の構造』は、柄谷行人による、ある意味で人類の未来への預言書である。その預言(筆者の考察)を我々凡庸な読者に理解させるためには、徹底的に人類の歴史について丁寧に細やかに説明必要があった。もちろん柄谷氏が注目した「交換様式」という概念を軸にして。そして、生まれたのが『世界史の構造』という、氏にしては珍しく、網羅的かつ構造的な大著である。
おそらく、あまりに刺激的な名著であるため、世界中から反響があったであろうし、また、筆者としては一つの軸を中心にブレなく一冊の書物にまとめる必要に迫られ、多くの派生的な考えを削ることにならざるを得なかった。『世界史の構造』発表後、2011.3.11東日本大震災・福島第一原発事故が起こり、新たな考えを持つとともに、削除された問題を語りたい(書きたい)という欲望が抑えられなくなった。その結果、新たに150枚の論文を書き、多方面の識者との数多くの対談をまとめ、上梓されたのが、本書『「世界史の構造」を読む』である。
対談の相手は、政治学者・小説家・元外交官・宗教学者など多岐に渡り、多くの識者が『世界史の構造』に示唆を受けたことを述べた上で、新たに質問をし持論を展開する、さらにそれに対する柄谷氏の解答・現在における考察を述べる。
巧妙な搾取システムである資本主義が限界を迎えつつある現在で、もうすでに第三世界(植民地化する場所・搾取する国)を失いつつある帝国が僅かなる差異を求める結果、世界戦争が訪れる。そして、その後に何が起こるか。それはB(略取と再分配)やC(商品交換)によって抑圧されていたA(互酬)が回帰するの交換様式Dの世界(「カント」の「世界共和国」)が訪れるといいうのだ。そのために、日本ができることは9条を実行すること、つまり国連に軍事力を移管することである、と。
自由=遊動民的=誰からの支配もない☞コミュニズム的アソシエーションの到来。